OBの山行記録・ 2007年4月8日 (日)
守門大岳(1432.4m)

●2007年4月1日(日)(1ー0)
【ルート】
二分=(大平)=(長峰)=(保久礼小屋)=守門大岳
【メンバ】
L:山森聡(1986入部)、M:石橋岳志(1982入部)、清原実(1986入部)

●2007年4月1日(日)(1ー0)
【ルート】
二分=(大平)=(長峰)=(保久礼小屋)=守門大岳
【メンバ】
L:山森聡(1986入部)、M:石橋岳志(1982入部)、清原実(1986入部)
【行程】
4月1日(日)(曇)二分(8:10)→大平(9:40)→長峰(9:45)→保久礼小屋(10:10-25)→守門大岳(12:20-40)→保久礼小屋(13:10-20)→長峰(13:40)→大平(14:00)→二分(14:20)
【地図】 (五万図)守門岳
【記録】
今年の4月1日(日)に、「東洋一の大雪庇」と評判の、守門の大岳にスキー山行に行ってきた。昨年の4月1日は、守門岳(袴岳)にスキー山行にきている。標高が低い(1537.2m)のに「雪の砂漠」といわれるだけあって、辺り一面、真っ白だったのが印象深かった。雪不足の今年でも、守門なら雪があるかも知れないと思い、1年振りに同じ山域にやってきた。土曜日(3/31)の雨と、月曜日(4/2)の雨の合間を縫って、山行を楽しむことができた。

前日は清原ババア宅(東京)でC0(シーゼロ)し、3:00出発。東京は桜が満開だ。高速を走って、登山口の二分には6:30に到着する。前日からの雨は止んできているものの、まだ時折、小雨がぱらついている。天気は次第に回復に向かっていくとの予報なので、時間待ちをして、8:10に出発した。人気の山スキーコースのようで、時間待ちをしている間にも、次々、車が到着し、入山していく。予想していたよりも、雪の量は多い。

予想していたよりは、雪の量が多いものの、例年なら埋まっているであろう沢が、口を空けていたりする。例年なら、大平を回らずに、沢型をショートカットして登れるのであろうが、今年は、林道を忠実に大平を回っていく。長峰までは、沢沿いに登っていく。写真は、シール歩行する清原ババア。

2時間も休まずに歩いて、保久礼小屋に到着し、休憩する。保久礼小屋はコンクリート造りの小屋で、ちょっと薄気味悪くて積極的に泊まりたいとは思わない。もう少し登ったところのブナの疎林の中にあった、避難小屋(木造)の方が、泊まるには快調そうだ。

保久礼小屋から守門大岳山頂までも、2時間近く、休まずに頑張って歩いた。天気は徐々に回復し、ガスの中だった山頂も、到着した頃には、ときどきガスが晴れた。しかし、ー10℃で風は強い。先に着いた石橋兄と清原ババアは、ツエルト被って休んでいた。写真は、守門大岳山頂にて。石橋兄(左)と清原ババア(右)。

守門大岳山頂にて。清原ババア(左)と山森(右)。この日は、約20数人が、スノーシューや山スキー、テレマークスキーで、守門大岳に登頂したと思われる。昨年の大原スキー場から守門岳(袴岳)のルートよりも、今年の二分から守門大岳のルートの方が、スキーが楽しめる斜面が多い。

東洋一の大雪庇と、清原ババアの滑り。

守門大岳山頂直下の大斜面を気持ち良く滑り降りる石橋兄(手前:テレマーク)と清原ババア(奥:山スキー)。二人ともスキーが上手なので、なかなか絵になる。

Co1100m付近のブナの疎林を滑る石橋兄。降雨直後のシャーベット雪なので、雪質は良くない。これがパウダーだったらどんなに気持ちが良いだろうと想像しながら滑る。しかし、雪不足の今年で4月にこれだけ雪があるので文句を言ってはバチが当たる。

保久礼小屋でシールを付け直して、登り返す。しばらくあるいて、シールを外す。振り返ると守門大岳や、滑ってきた尾根が見渡せた。

お決まりの温泉は、旧守門村の魚沼市営の守門温泉「青雲館」。日帰り入浴500円。魚沼市は、中越地震(2004年10月23日)直後の2004(H16)年11月1日に、新潟県北魚沼郡堀之内町、小出町、湯之谷村、広神村、守門村、入広瀬村の2町4村が合併して誕生した。昨年の4月1日は旧入広瀬村から入山し、旧入広瀬村の温泉で疲れを癒した。今年の4月1日は旧守門村から入山し、旧守門村の温泉で疲れを癒した。
(報告:山森 聡)
4月1日(日)(曇)二分(8:10)→大平(9:40)→長峰(9:45)→保久礼小屋(10:10-25)→守門大岳(12:20-40)→保久礼小屋(13:10-20)→長峰(13:40)→大平(14:00)→二分(14:20)
【地図】 (五万図)守門岳
【記録】
今年の4月1日(日)に、「東洋一の大雪庇」と評判の、守門の大岳にスキー山行に行ってきた。昨年の4月1日は、守門岳(袴岳)にスキー山行にきている。標高が低い(1537.2m)のに「雪の砂漠」といわれるだけあって、辺り一面、真っ白だったのが印象深かった。雪不足の今年でも、守門なら雪があるかも知れないと思い、1年振りに同じ山域にやってきた。土曜日(3/31)の雨と、月曜日(4/2)の雨の合間を縫って、山行を楽しむことができた。

前日は清原ババア宅(東京)でC0(シーゼロ)し、3:00出発。東京は桜が満開だ。高速を走って、登山口の二分には6:30に到着する。前日からの雨は止んできているものの、まだ時折、小雨がぱらついている。天気は次第に回復に向かっていくとの予報なので、時間待ちをして、8:10に出発した。人気の山スキーコースのようで、時間待ちをしている間にも、次々、車が到着し、入山していく。予想していたよりも、雪の量は多い。

予想していたよりは、雪の量が多いものの、例年なら埋まっているであろう沢が、口を空けていたりする。例年なら、大平を回らずに、沢型をショートカットして登れるのであろうが、今年は、林道を忠実に大平を回っていく。長峰までは、沢沿いに登っていく。写真は、シール歩行する清原ババア。

2時間も休まずに歩いて、保久礼小屋に到着し、休憩する。保久礼小屋はコンクリート造りの小屋で、ちょっと薄気味悪くて積極的に泊まりたいとは思わない。もう少し登ったところのブナの疎林の中にあった、避難小屋(木造)の方が、泊まるには快調そうだ。

保久礼小屋から守門大岳山頂までも、2時間近く、休まずに頑張って歩いた。天気は徐々に回復し、ガスの中だった山頂も、到着した頃には、ときどきガスが晴れた。しかし、ー10℃で風は強い。先に着いた石橋兄と清原ババアは、ツエルト被って休んでいた。写真は、守門大岳山頂にて。石橋兄(左)と清原ババア(右)。

守門大岳山頂にて。清原ババア(左)と山森(右)。この日は、約20数人が、スノーシューや山スキー、テレマークスキーで、守門大岳に登頂したと思われる。昨年の大原スキー場から守門岳(袴岳)のルートよりも、今年の二分から守門大岳のルートの方が、スキーが楽しめる斜面が多い。

東洋一の大雪庇と、清原ババアの滑り。

守門大岳山頂直下の大斜面を気持ち良く滑り降りる石橋兄(手前:テレマーク)と清原ババア(奥:山スキー)。二人ともスキーが上手なので、なかなか絵になる。

Co1100m付近のブナの疎林を滑る石橋兄。降雨直後のシャーベット雪なので、雪質は良くない。これがパウダーだったらどんなに気持ちが良いだろうと想像しながら滑る。しかし、雪不足の今年で4月にこれだけ雪があるので文句を言ってはバチが当たる。

保久礼小屋でシールを付け直して、登り返す。しばらくあるいて、シールを外す。振り返ると守門大岳や、滑ってきた尾根が見渡せた。

お決まりの温泉は、旧守門村の魚沼市営の守門温泉「青雲館」。日帰り入浴500円。魚沼市は、中越地震(2004年10月23日)直後の2004(H16)年11月1日に、新潟県北魚沼郡堀之内町、小出町、湯之谷村、広神村、守門村、入広瀬村の2町4村が合併して誕生した。昨年の4月1日は旧入広瀬村から入山し、旧入広瀬村の温泉で疲れを癒した。今年の4月1日は旧守門村から入山し、旧守門村の温泉で疲れを癒した。
(報告:山森 聡)
- コメント (3)
OBの山行記録・ 2007年3月25日 (日)
●和賀山塊 高下岳(こうげだけ)1322.8m

【年月日】2007年3月17日(土)〜18日(日)
【ルート】岩手県西和賀町沢内川舟〜高下岳(往復)
【メンバ】銭谷竜一(1990入部)、北川徹(山スキー部OB)、深田直之(山スキー部OB)
【行 程】3月17日 森の館かっこう(10:00) 高下岳(こうげだけ)南東尾根1100mC1(13:40)
3月18日 C1(6:25) 高下岳(7:10〜7:30) C1(7:45〜9:30)〜森の館かっこう(10:30)

【年月日】2007年3月17日(土)〜18日(日)
【ルート】岩手県西和賀町沢内川舟〜高下岳(往復)
【メンバ】銭谷竜一(1990入部)、北川徹(山スキー部OB)、深田直之(山スキー部OB)
【行 程】3月17日 森の館かっこう(10:00) 高下岳(こうげだけ)南東尾根1100mC1(13:40)
3月18日 C1(6:25) 高下岳(7:10〜7:30) C1(7:45〜9:30)〜森の館かっこう(10:30)
山深い奥羽山脈脊梁の山々でも秘境性が高いといわれる和賀山塊。正月のNHKで、秋田側のブナ林が紹介されていたが、岩手側からの記録はほとんど見ない。今回は函館、仙台、一関から集ったメンバーで岩手側からのアプローチを試みた。
3/17 晴れ時々雪
盛岡駅で集合し、深田車に乗り込む。北川とは4〜5年ぶり、深田とは第3次カムチャツカ以来10年ぶりの山行。みんな相変わらずである。
1時間ほどで旧沢内村に到着。最寄りのバス停は「開拓地」とあり、東北の山村というより、北海道のような雰囲気が感じられる。現在は地ビール工場ができて、「銀河高原」と呼ばれている。

大荒沢川沿いの最終人家「森の館かっこう」横で準備をしていると、管理人さんから山の様子を聞くことができた。川の渡渉もできるようなので、当初予定していた、左岸側の尾根から脊梁の稜線に乗る計画を高下岳経由に変更する。また、緊急下山したときのために、古民家を改築した施設を開放しておいてくれるとのこと。親切に感謝しながら出発。

教えてもらったとおりに牧場脇の渓畔林を抜けて工事中の砂防施設の下で渡渉し、尾根に取り付く。傾斜の緩い広い尾根を快調に登っていくと、道標のようにブナの大木がそびえている。

ある大木にはカタカナで鉈目が記してあった。「ユキヲ」と表記してあるので、昭和30〜40年代以前に彫られたものだろうか?奥羽山脈を自在に歩いていたマタギの手によるものだろうか?と想像も膨らむ。

標高900〜1000m付近は大きな木が多く、気持ちよく歩ける。1000m以上ではブナの樹高が低くなり、低い位置から多くの枝が分かれている。「矮性ブナ」といい、この山域の特徴的な植生らしい。

標高1100m付近の、判りにくい尾根の分岐にイグルーを作り、下りの目印とする。10年ぶりなので時間がかかってしまったが、2時間強で3人分の快適なイグルーができた。銀河高原を見渡せるいい天場だ。

天気もまあまあなので、イグルーの脇で焚火を起こし、生姜入りカレー雑炊をつくる。やっぱり山のなかで食う飯はうまい。
3/18 雪・風 のち曇時々雪
夜中風が強く吹いていたが、イグルーの中は快適に眠れた。朝も風はやまず、視界もあまりない。天気の回復も見込めそうにないが、高下岳はすぐそこだ。スキーを履いて出発する。

高下岳頂上付近から先の稜線はクラストしているし、悪い視界のなかで無理に朝日岳までロングアタックすることはなかろう、と引き返すことにする(写真:頂上にて。左から深田、北川。)
樹林限界より上の1300〜1200mは快調な斜面で、イグルーまであっという間に帰着する。
登頂をビールで祝い、お茶を飲んでのんびりしていると、カンジキ履きの単独行の登山者が登ってきた。聞けば年齢は70歳で、年に何度か登りにきているらしい。話もそこそこに別れて、下山を開始する。


標高750mくらいまでは快調な樹林帯スキーを楽しむ。その下は灌木が多く、山スキー部の2人は小回りでかわしながら下っていくが、銭谷は怪我しないようにのんびりとついていく。
昼前に下山すると、楽しみにしていた「森の館かっこう」のネパールカレーは、冬季間銀河高原ビールの工場に併設されたホテルで出張営業しているとのこと。リゾートホテルの爽やかなレストランで生姜の利いたネパールカレーと温泉を楽しみ、地ビールを土産に帰路についた。
当初もくろんでいた羽後朝日岳までは行けなかったが、この山域は植生が標高200mくらいの間隔ではっきり変わるし、沢も深く、面白そうだ。残雪期や沢登りでも楽しめそうなので、また来よう。
3/17 晴れ時々雪
盛岡駅で集合し、深田車に乗り込む。北川とは4〜5年ぶり、深田とは第3次カムチャツカ以来10年ぶりの山行。みんな相変わらずである。
1時間ほどで旧沢内村に到着。最寄りのバス停は「開拓地」とあり、東北の山村というより、北海道のような雰囲気が感じられる。現在は地ビール工場ができて、「銀河高原」と呼ばれている。

大荒沢川沿いの最終人家「森の館かっこう」横で準備をしていると、管理人さんから山の様子を聞くことができた。川の渡渉もできるようなので、当初予定していた、左岸側の尾根から脊梁の稜線に乗る計画を高下岳経由に変更する。また、緊急下山したときのために、古民家を改築した施設を開放しておいてくれるとのこと。親切に感謝しながら出発。

教えてもらったとおりに牧場脇の渓畔林を抜けて工事中の砂防施設の下で渡渉し、尾根に取り付く。傾斜の緩い広い尾根を快調に登っていくと、道標のようにブナの大木がそびえている。

ある大木にはカタカナで鉈目が記してあった。「ユキヲ」と表記してあるので、昭和30〜40年代以前に彫られたものだろうか?奥羽山脈を自在に歩いていたマタギの手によるものだろうか?と想像も膨らむ。

標高900〜1000m付近は大きな木が多く、気持ちよく歩ける。1000m以上ではブナの樹高が低くなり、低い位置から多くの枝が分かれている。「矮性ブナ」といい、この山域の特徴的な植生らしい。

標高1100m付近の、判りにくい尾根の分岐にイグルーを作り、下りの目印とする。10年ぶりなので時間がかかってしまったが、2時間強で3人分の快適なイグルーができた。銀河高原を見渡せるいい天場だ。

天気もまあまあなので、イグルーの脇で焚火を起こし、生姜入りカレー雑炊をつくる。やっぱり山のなかで食う飯はうまい。
3/18 雪・風 のち曇時々雪
夜中風が強く吹いていたが、イグルーの中は快適に眠れた。朝も風はやまず、視界もあまりない。天気の回復も見込めそうにないが、高下岳はすぐそこだ。スキーを履いて出発する。

高下岳頂上付近から先の稜線はクラストしているし、悪い視界のなかで無理に朝日岳までロングアタックすることはなかろう、と引き返すことにする(写真:頂上にて。左から深田、北川。)
樹林限界より上の1300〜1200mは快調な斜面で、イグルーまであっという間に帰着する。
登頂をビールで祝い、お茶を飲んでのんびりしていると、カンジキ履きの単独行の登山者が登ってきた。聞けば年齢は70歳で、年に何度か登りにきているらしい。話もそこそこに別れて、下山を開始する。


標高750mくらいまでは快調な樹林帯スキーを楽しむ。その下は灌木が多く、山スキー部の2人は小回りでかわしながら下っていくが、銭谷は怪我しないようにのんびりとついていく。
昼前に下山すると、楽しみにしていた「森の館かっこう」のネパールカレーは、冬季間銀河高原ビールの工場に併設されたホテルで出張営業しているとのこと。リゾートホテルの爽やかなレストランで生姜の利いたネパールカレーと温泉を楽しみ、地ビールを土産に帰路についた。
当初もくろんでいた羽後朝日岳までは行けなかったが、この山域は植生が標高200mくらいの間隔ではっきり変わるし、沢も深く、面白そうだ。残雪期や沢登りでも楽しめそうなので、また来よう。
- コメント (3)
部報解説・ 2007年3月24日 (土)
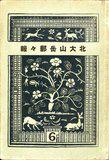 1937年1月末の(第一次)ペテガリ冬季初登頂作戦の遠征報告がメイン記事。残念ながら途中引き返しだが、これまでにない大企画だった。このあと1943年の成功(部報8号に報告)の前には1940年の雪崩遭難という苦難があるがそれは7号での報告。時代はペテガリまっしぐらだが、冬期のトヨニ、ピリカ、神威岳、1823峰の初登頂記もある。
1937年1月末の(第一次)ペテガリ冬季初登頂作戦の遠征報告がメイン記事。残念ながら途中引き返しだが、これまでにない大企画だった。このあと1943年の成功(部報8号に報告)の前には1940年の雪崩遭難という苦難があるがそれは7号での報告。時代はペテガリまっしぐらだが、冬期のトヨニ、ピリカ、神威岳、1823峰の初登頂記もある。また海外記録が豪華だ。北千島、中部千島(新知島の新知岳、松輪島の芙蓉岳など初登)、択捉の散布岳初登、樺太の日ソ国境周辺の山散策、ほか朝鮮の冠帽峰、台湾の新高山や合歓山はもちろん、タロコ峡より中央尖山、南湖大山を「蕃人」たちの案内で登り、山稜でゾンメルスキーをやっている。東亜の山へ存分に足を延ばす1930年代。京大が白頭山、大興安嶺、京城帝大や早稲田が冠帽峰を登っている。数年後に迫る世界戦争が無情だ。これらは次回後篇で紹介する。
部報6号(1938年)前半編
● ペテガリ岳ー嚴冬期におけるー
・ まへがき 葛西晴雄
・ 準備 有馬洋
・ 經過 有馬洋
・ 冬期登攀用品に就いて 林和夫
・ 食料ノートより 岡彦一、中野龍雄
・ 氣象について 星野昌平
● 冬の南日高連峰
・ 豐似川よりピリカヌプリ山へ 湊正雄
・ 一月の神威岳 葛西晴雄
【総評】
1935/10月から1938/4月の記録。記事140p、年報119pの合計259p。編集委員は10名の連名。編集後記は葛西晴雄。これまでの部報の挿入写真は、風景が多かったが、今号ではペテガリ隊のキャンプ地での何気ない焚き火の写真など、気取らぬものが増えている。
【時代】
1935年:積雪期、北アルプスでは鹿島槍北壁右ルンゼ(浪速高)、剣岳小窓尾根(立教・早稲田)、東大谷中俣、本谷、池ノ谷右俣(以上立教)、穂高ジャンダルム飛騨尾根(東京農大)などが学生山岳部によって次々初登攀された。北岳バットレス第4尾根初登(東京商科大)もこの夏。1月に加藤文太郎が、立山から針ノ木岳へ黒部横断の厳冬期単独縦走。極地法を身につけたAACKは朝鮮白頭山遠征をする。第5次エベレスト遠征(英)・シプトン隊
1936年:積雪期剱尾根初登(早稲田)、立教大が日本初のヒマラヤ登山ナンダ・コット(6861m)初登頂。京大AACK中部大興安嶺踏査。加藤文太郎北鎌尾根で遭難死。エベレスト第6次隊。ティルマン(英)、ナンダデヴィー初登。バウアー(独)、シニオルチュー初登。世間は2.26事件。日独防共協定。西安事件で国共合作。スペイン戦争。ベルリンオリンピック。
1937年:北岳バットレス第4尾根積雪期初登(東京商科大)、鹿島槍荒沢奥壁積雪期初登(東京商科大)など。第3次ナンガパルバット(独)で16人雪崩死。
世間は遂に蘆溝橋事件、日中戦争始まる、12月の南京陥落後も重慶政府と戦争は続く。スペインではナチスがゲルニカ空爆。
1938年:西穂〜奥穂1月初縦走(慶応大)、前穂北尾根松高ルート初登。北穂滝谷第4尾根単独初登(松濤明)など。第7次エベレスト(英)・ティルマン隊。バウアー(独)、第4次ナンガパルバット。ハウストン(米)、K2。いずれも届かず。ハラーら(独)アイガー北壁初登。世間では国民総動員法施行で戦争体制に。日本軍が重慶空爆、広東占領、武漢占領。ドイツがオーストリアを併合。
● ペテガリ岳ー嚴冬期におけるー
・ まへがき 葛西晴雄
・ 準備 有馬洋
・ 經過 有馬洋
1937年1月28日から2月7日まで四班十一名で挑んだ厳冬期初登。1934年入部の三年目葛西、林、中野(龍)、有馬(洋)らを主体とし、一年目の橋本(ヤンチョ)、OBで卒業後十年たつ坂本直行もいる。札内川から入りコイカクシュサツナイ岳より稜線を往復の計画だが、悪天のため1599峰(初登)までで断念した。「 かく此の山が冬期に於て再三の試みをも退け今日なほ未知の姿として山脈の奧深く殘されてゐる主な理由としては、種々の不利なる條件のために澤を最後迄利用して頂上への登高を行ふことの困難なる事を擧げなければならない。そして利用出來る澤の上から頂上迄長い間尾根傳ひキヤンプを進めていくのである。」「三月にはその氣温、氣象的關係から雪崩の危險を増し、或いは不規則な雪庇を作り叉例年に依ると概して荒天が多いやうである。澤の結氷状態、尾根上の雪の堅さからみても最も寒氣の烈しい二月が最良であることよりして、」この時期が選ばれた。前の夏から二パーティーが此の山域に入って研究し七人用かまぼこ型テントや小型テントなどを考案製作した。そしてルームには珍しい極地法的な「サポーティングシステム」を取り入れている。が、天気周期悪く、新兵器のテントも潰され、1599m峰までで退却した。
このパーティーの中から、1940年再びペテガリ(第二次)に挑戦した有馬、葛西が雪崩で帰らず、橋本がかろうじて助かった。
・ 冬期登攀用品に就いて 林和夫
今回の大作戦では初めて厳冬日高の稜線上に泊まるため、コイカク山頂のC2には蒲鉾型テントを、ヤオロマップ山頂下には耐風型変形三角テントを作って、初使用した。一方樹林帯のC1では、いまも変わらぬ三角テントで、支柱を現地で調達、中にタンネを敷き詰めるという創部以来の方法が部報では初めて詳しく記述されている(図解入り)。しかし梁を載せ、紐で結わえ、吊り下げたのはこのときが初だったようだ「立ち木はいくらでも豊富にあるのだからと云ふわけで、ペテガリ行のベースキャンプではこれを吊り下げ式にして使用してみた。」。C2,C3の新型テントも、暴風にあっけなく壊され、敗退の一要因になった。樹林帯からのロングアタックでは届かない初めての山頂であるペテガリのために、苦労している。これらドームテントの骨は、トンキン竹や槲(かしわ)の木だ。何故、ペテガリが未踏峰として残ったのか、こういう面からもよくわかる。ペテガリ岳は、ルームが初めて樹林帯ではなく、白い稜線に泊まる必要に迫られた山だった。
当時、ヒマラヤを目指して1931〜2年に京大山岳部が富士山で日本初の極地方登山を実践し、1930年代を通じ、慶応や早稲田の山岳部が、槍穂高、剱でやはり初めて白い稜線での高所露営を実践し始めていた時代である。どこもイギリスのエベレスト遠征隊などの情報を元に手作り試行錯誤で研究していた。
その他の装備も、タンネの葉が敷けないC2,C3では初めてマットレスを用いた。「一人につき巾四〇糎長さ100糎のもの一枚を用ひ、微粒コルクの入つた巾3.5糎(センチ)の部分と、入らない巾1.2糎の部分とが連續して100糎になつてゐるのである。一人用一枚230匁(一匁は3.75グラム、一貫は3.75キログラム)になり非常に優秀なものである。」
オーバーシューズも今回に備え美瑛岳の合宿で初めて試したところ、「零下三〇度と云ふ寒さに加へて烈風が吹いた爲、足を凍傷した者多かつたが、これを用ひてたものは足の冷たさをさへ感じず、優秀性を裏書きした。」シーデポの旗もタダの赤ではなく、「ソビエト北極探検隊に倣つて黄色の入つた赤、即ち明るいオレンヂ色を」用いて遠くからも吹雪の中でもよく見えたという。ベンジンのストーブとアルコールストーブを較べ、火力でアルコールを採用している。
「吹き晒しの日高の尾根の夜、外に出て小用をする等到底不可能な事だつた。それで始めは交互に、天幕の底布に開けてある塵出しの穴ですましたが後にはアルコールを入れて行つた一立入りの罐ですました。」なんと!いまに伝わるテント内床ション、ビニションのルーツはここにあった。
・ 食料ノートより 岡彦一、中野龍雄
食料の詳細が書かれているのは部報では初めて。朝は餅入りみそ汁、夜はご飯と乾燥野菜やベーコン入りみそ汁で、基本はみそ汁味だ。このころはインスタントラーメンや、手頃なカレールーがまだ無かったようだ。「京都某商店製の味付きうどん」というのが、煮るだけの簡単麺のようだ。昼の行動食はフランスパンが主流。
・ 氣象について 星野昌平
ペテガリ敗退の気象分析をしている。当時は当然ながら携帯ラジオはなかった。現場では風向風力観測と、気圧計を使っての情報で判断している。天気図を見るという方法ではないので、風向には非常に敏感だ。
● 冬の南日高連峰
・ 豐似川よりピリカヌプリ山へ 湊正雄
「ピリカと云つてもそんなに有名な山ではないが之は日高山脈も南端に近いヌピナイ川の上流にある山である。」から始まる1935年末からの冬期初登記。十日間、本野、湊、葛西の三人パーティー。当時のピリカはこんな認識だった。豊似で牧場をしている坂本直行は忙しくて参加を断念。パーティーは直行宅にC0(前夜泊)する。
「烈しい鋭さ等といふものは勿論求められないが、何處となくゆるせないものを包んでゐる大きな山容はペテガリと共に高く買はる可きものである。事實、日高と十勝の國境線の上に竝んだ大小幾多の峰頂の中で、最後の鞍部から頂上まで三〇〇米以上もの急騰を強ひるものは、情けない話であるが、此の山を除いては一つも無いのである。しかしそんな事はどうでも良い。私達がはるばる此の名も良く知られてゐない山に出掛けていつたのは唯この山に魅せられたが故であり、ひどく愛したからであつた。」ルートは豊似川から。入山時は雪が少なかったのに、中流部標高580m附近で「馬鹿雪」に降られ停滞。ここをBCとしてロングアタックする作戦に変える。「長い毛皮の長靴は愚か腰も沒する樣な四尺からある豪雪だ。其んなひどい雪では何も出來はしない。寢て落ち着くのを待つのが一番だといふのでシュラーフに入ると眠つてしまつた。不精者が三人揃つたので歩かない時は飯もつくらない事になつてゐた。」パーティーの雰囲気が匂い立つ一文である。
いくつもの滝を捲き、沢を詰め、トヨニ南峰1493m(当時はトヨヰ岳1520mと呼んでいたようだ)東のコルにシーデポ、ピリカをアタックする。朝四時前出発の十七時間半行動だった。「それから翌日の夕方おそく、五里の道を再びトヨニの友の所に歸つて行つて、心から祝福された。牝牛と、よごろく號(馬の名)の間に吊り下げられた直行氏得意の吊り風呂で、痩せ細つた體がランプに照らされてゐた。」卒業後十年経っている坂本直行の、山への意欲はまだ現役に影響を与え続けている。ピリカは南からが格好良いという方針で、ヌピナイ川からを避け、豊似川に登路をとった。
・ 一月の神威嶽 葛西晴雄
1937年暮れからの十日間。ヌピナイ川からの神威岳冬期初登記。入山六日目に尾根に出て、七日目登頂。葛西晴雄、中野征紀、有馬洋。全体に、少しとぼけた面白い記録だ。
「笹の密生した斜面や倒木と戰ひながら_いた。笹の斜面を登る時はルックと身體の重量の爲屡々一寸した加減で足がツルンと滑つて掬はれ、その度毎に朝食べた二切分の餅に相當する位のカロリーが豫期せずして一瞬に失はれたやうに感ぜられるのは癪にさはつた。」この気持ち、よくわかる。渡渉の際、「私達は此の時とばかり用意してきたゴム長靴の股迄來るやつを穿いて渡つたが、しかしかゝる天氣の良い暖かい日の下では、スキー鞜にゲートルのまゝ淺瀬を狙つて走り渡つた長髮兄(中野征紀氏のこと)の方が結局時間的に遙かに頭が良い事になつた。」これもよく経験する一幕。
一度ラッセルして、余計な荷物を取りにもどって運ぶ方法を、ヴィーダーコンメンメトーデ(wieder kommen methode)という怪しげなドイツ語で呼び始めたのもこの山行からのようだ。現在、これは「ビーコン」などと呼ばれている。
ヌピナイの函の手前にBCを作り、函地帯は軽い身で、ザイルなど出しながら捲いて進む。ソエマツとピリカの中間のポコから降りている尾根を登ろうとその基部(上二股のこと)にアタックキャンプを構える。ここで一停滞のあと、この尾根の標高1340mにアタックキャンプを全身させる。翌日、ここからロングアタック。厳冬初登頂のソエマツ山頂から見た、神威岳の美しさに賛辞を惜しまない。この光景を見たのは、彼らが初めてだ。写真で見た上で登った僕らでさえ、息を呑む美しさだった。
「午後零時卅分、遂に神威の頂上に立つことができた。之でやつと來たんだ、私達は默つて互ひに祝福し合つた。ヤンチョ(橋本誠二氏)送る處のチヨコレートが取り出された。私達は未だ誰にも示されなかつた此處からの嚴な冬の景色を眺めて何故とはなしに嬉しかつた。此處に一つの足蹟を殘し得た事に無上の喜びを感じた。」結局十四時間行動。この時代の日高の未踏峰山行は、沢を詰め、最終キャンプから軽い身で10時間以上のロングアタックをかけて樹林帯に戻る。その典型的な形式である。何か潔い、知力と体力を尽くす登山スタイルだと思う。
以下は後半編に続く
●忠別川遡行 石橋恭一郎
● ヤオロマップ川遡行 豐田春滿
● 新しき山旅より
・ 音更川遡行 中村粂夫
・ 蘆別岳北尾根の池 鈴木限三
・ 散布岳 岡彦一
・ ペテガリ・ソナタ 有馬洋
・ 樺太の山雜感 岡彦一
・ 北部日高山脈の旅 山崎春雄
・ 一八二三米峰 中野龍雄
・ 蕃人 岡彦一
● 最近の十勝合宿について
ー冬期合宿覺え書きの一つとしてー 朝比奈英三
● 追悼
・懷舊 伊藤秀五郎
・ 伊藤周一君 福地文平
年報(1935/10−1938/4)
写真13点、スケッチ4点、地図3点
(解説前編/中編/後編)
1935/10月から1938/4月の記録。記事140p、年報119pの合計259p。編集委員は10名の連名。編集後記は葛西晴雄。これまでの部報の挿入写真は、風景が多かったが、今号ではペテガリ隊のキャンプ地での何気ない焚き火の写真など、気取らぬものが増えている。
【時代】
1935年:積雪期、北アルプスでは鹿島槍北壁右ルンゼ(浪速高)、剣岳小窓尾根(立教・早稲田)、東大谷中俣、本谷、池ノ谷右俣(以上立教)、穂高ジャンダルム飛騨尾根(東京農大)などが学生山岳部によって次々初登攀された。北岳バットレス第4尾根初登(東京商科大)もこの夏。1月に加藤文太郎が、立山から針ノ木岳へ黒部横断の厳冬期単独縦走。極地法を身につけたAACKは朝鮮白頭山遠征をする。第5次エベレスト遠征(英)・シプトン隊
1936年:積雪期剱尾根初登(早稲田)、立教大が日本初のヒマラヤ登山ナンダ・コット(6861m)初登頂。京大AACK中部大興安嶺踏査。加藤文太郎北鎌尾根で遭難死。エベレスト第6次隊。ティルマン(英)、ナンダデヴィー初登。バウアー(独)、シニオルチュー初登。世間は2.26事件。日独防共協定。西安事件で国共合作。スペイン戦争。ベルリンオリンピック。
1937年:北岳バットレス第4尾根積雪期初登(東京商科大)、鹿島槍荒沢奥壁積雪期初登(東京商科大)など。第3次ナンガパルバット(独)で16人雪崩死。
世間は遂に蘆溝橋事件、日中戦争始まる、12月の南京陥落後も重慶政府と戦争は続く。スペインではナチスがゲルニカ空爆。
1938年:西穂〜奥穂1月初縦走(慶応大)、前穂北尾根松高ルート初登。北穂滝谷第4尾根単独初登(松濤明)など。第7次エベレスト(英)・ティルマン隊。バウアー(独)、第4次ナンガパルバット。ハウストン(米)、K2。いずれも届かず。ハラーら(独)アイガー北壁初登。世間では国民総動員法施行で戦争体制に。日本軍が重慶空爆、広東占領、武漢占領。ドイツがオーストリアを併合。
● ペテガリ岳ー嚴冬期におけるー
・ まへがき 葛西晴雄
・ 準備 有馬洋
・ 經過 有馬洋
1937年1月28日から2月7日まで四班十一名で挑んだ厳冬期初登。1934年入部の三年目葛西、林、中野(龍)、有馬(洋)らを主体とし、一年目の橋本(ヤンチョ)、OBで卒業後十年たつ坂本直行もいる。札内川から入りコイカクシュサツナイ岳より稜線を往復の計画だが、悪天のため1599峰(初登)までで断念した。「 かく此の山が冬期に於て再三の試みをも退け今日なほ未知の姿として山脈の奧深く殘されてゐる主な理由としては、種々の不利なる條件のために澤を最後迄利用して頂上への登高を行ふことの困難なる事を擧げなければならない。そして利用出來る澤の上から頂上迄長い間尾根傳ひキヤンプを進めていくのである。」「三月にはその氣温、氣象的關係から雪崩の危險を増し、或いは不規則な雪庇を作り叉例年に依ると概して荒天が多いやうである。澤の結氷状態、尾根上の雪の堅さからみても最も寒氣の烈しい二月が最良であることよりして、」この時期が選ばれた。前の夏から二パーティーが此の山域に入って研究し七人用かまぼこ型テントや小型テントなどを考案製作した。そしてルームには珍しい極地法的な「サポーティングシステム」を取り入れている。が、天気周期悪く、新兵器のテントも潰され、1599m峰までで退却した。
このパーティーの中から、1940年再びペテガリ(第二次)に挑戦した有馬、葛西が雪崩で帰らず、橋本がかろうじて助かった。
・ 冬期登攀用品に就いて 林和夫
今回の大作戦では初めて厳冬日高の稜線上に泊まるため、コイカク山頂のC2には蒲鉾型テントを、ヤオロマップ山頂下には耐風型変形三角テントを作って、初使用した。一方樹林帯のC1では、いまも変わらぬ三角テントで、支柱を現地で調達、中にタンネを敷き詰めるという創部以来の方法が部報では初めて詳しく記述されている(図解入り)。しかし梁を載せ、紐で結わえ、吊り下げたのはこのときが初だったようだ「立ち木はいくらでも豊富にあるのだからと云ふわけで、ペテガリ行のベースキャンプではこれを吊り下げ式にして使用してみた。」。C2,C3の新型テントも、暴風にあっけなく壊され、敗退の一要因になった。樹林帯からのロングアタックでは届かない初めての山頂であるペテガリのために、苦労している。これらドームテントの骨は、トンキン竹や槲(かしわ)の木だ。何故、ペテガリが未踏峰として残ったのか、こういう面からもよくわかる。ペテガリ岳は、ルームが初めて樹林帯ではなく、白い稜線に泊まる必要に迫られた山だった。
当時、ヒマラヤを目指して1931〜2年に京大山岳部が富士山で日本初の極地方登山を実践し、1930年代を通じ、慶応や早稲田の山岳部が、槍穂高、剱でやはり初めて白い稜線での高所露営を実践し始めていた時代である。どこもイギリスのエベレスト遠征隊などの情報を元に手作り試行錯誤で研究していた。
その他の装備も、タンネの葉が敷けないC2,C3では初めてマットレスを用いた。「一人につき巾四〇糎長さ100糎のもの一枚を用ひ、微粒コルクの入つた巾3.5糎(センチ)の部分と、入らない巾1.2糎の部分とが連續して100糎になつてゐるのである。一人用一枚230匁(一匁は3.75グラム、一貫は3.75キログラム)になり非常に優秀なものである。」
オーバーシューズも今回に備え美瑛岳の合宿で初めて試したところ、「零下三〇度と云ふ寒さに加へて烈風が吹いた爲、足を凍傷した者多かつたが、これを用ひてたものは足の冷たさをさへ感じず、優秀性を裏書きした。」シーデポの旗もタダの赤ではなく、「ソビエト北極探検隊に倣つて黄色の入つた赤、即ち明るいオレンヂ色を」用いて遠くからも吹雪の中でもよく見えたという。ベンジンのストーブとアルコールストーブを較べ、火力でアルコールを採用している。
「吹き晒しの日高の尾根の夜、外に出て小用をする等到底不可能な事だつた。それで始めは交互に、天幕の底布に開けてある塵出しの穴ですましたが後にはアルコールを入れて行つた一立入りの罐ですました。」なんと!いまに伝わるテント内床ション、ビニションのルーツはここにあった。
・ 食料ノートより 岡彦一、中野龍雄
食料の詳細が書かれているのは部報では初めて。朝は餅入りみそ汁、夜はご飯と乾燥野菜やベーコン入りみそ汁で、基本はみそ汁味だ。このころはインスタントラーメンや、手頃なカレールーがまだ無かったようだ。「京都某商店製の味付きうどん」というのが、煮るだけの簡単麺のようだ。昼の行動食はフランスパンが主流。
・ 氣象について 星野昌平
ペテガリ敗退の気象分析をしている。当時は当然ながら携帯ラジオはなかった。現場では風向風力観測と、気圧計を使っての情報で判断している。天気図を見るという方法ではないので、風向には非常に敏感だ。
● 冬の南日高連峰
・ 豐似川よりピリカヌプリ山へ 湊正雄
「ピリカと云つてもそんなに有名な山ではないが之は日高山脈も南端に近いヌピナイ川の上流にある山である。」から始まる1935年末からの冬期初登記。十日間、本野、湊、葛西の三人パーティー。当時のピリカはこんな認識だった。豊似で牧場をしている坂本直行は忙しくて参加を断念。パーティーは直行宅にC0(前夜泊)する。
「烈しい鋭さ等といふものは勿論求められないが、何處となくゆるせないものを包んでゐる大きな山容はペテガリと共に高く買はる可きものである。事實、日高と十勝の國境線の上に竝んだ大小幾多の峰頂の中で、最後の鞍部から頂上まで三〇〇米以上もの急騰を強ひるものは、情けない話であるが、此の山を除いては一つも無いのである。しかしそんな事はどうでも良い。私達がはるばる此の名も良く知られてゐない山に出掛けていつたのは唯この山に魅せられたが故であり、ひどく愛したからであつた。」ルートは豊似川から。入山時は雪が少なかったのに、中流部標高580m附近で「馬鹿雪」に降られ停滞。ここをBCとしてロングアタックする作戦に変える。「長い毛皮の長靴は愚か腰も沒する樣な四尺からある豪雪だ。其んなひどい雪では何も出來はしない。寢て落ち着くのを待つのが一番だといふのでシュラーフに入ると眠つてしまつた。不精者が三人揃つたので歩かない時は飯もつくらない事になつてゐた。」パーティーの雰囲気が匂い立つ一文である。
いくつもの滝を捲き、沢を詰め、トヨニ南峰1493m(当時はトヨヰ岳1520mと呼んでいたようだ)東のコルにシーデポ、ピリカをアタックする。朝四時前出発の十七時間半行動だった。「それから翌日の夕方おそく、五里の道を再びトヨニの友の所に歸つて行つて、心から祝福された。牝牛と、よごろく號(馬の名)の間に吊り下げられた直行氏得意の吊り風呂で、痩せ細つた體がランプに照らされてゐた。」卒業後十年経っている坂本直行の、山への意欲はまだ現役に影響を与え続けている。ピリカは南からが格好良いという方針で、ヌピナイ川からを避け、豊似川に登路をとった。
・ 一月の神威嶽 葛西晴雄
1937年暮れからの十日間。ヌピナイ川からの神威岳冬期初登記。入山六日目に尾根に出て、七日目登頂。葛西晴雄、中野征紀、有馬洋。全体に、少しとぼけた面白い記録だ。
「笹の密生した斜面や倒木と戰ひながら_いた。笹の斜面を登る時はルックと身體の重量の爲屡々一寸した加減で足がツルンと滑つて掬はれ、その度毎に朝食べた二切分の餅に相當する位のカロリーが豫期せずして一瞬に失はれたやうに感ぜられるのは癪にさはつた。」この気持ち、よくわかる。渡渉の際、「私達は此の時とばかり用意してきたゴム長靴の股迄來るやつを穿いて渡つたが、しかしかゝる天氣の良い暖かい日の下では、スキー鞜にゲートルのまゝ淺瀬を狙つて走り渡つた長髮兄(中野征紀氏のこと)の方が結局時間的に遙かに頭が良い事になつた。」これもよく経験する一幕。
一度ラッセルして、余計な荷物を取りにもどって運ぶ方法を、ヴィーダーコンメンメトーデ(wieder kommen methode)という怪しげなドイツ語で呼び始めたのもこの山行からのようだ。現在、これは「ビーコン」などと呼ばれている。
ヌピナイの函の手前にBCを作り、函地帯は軽い身で、ザイルなど出しながら捲いて進む。ソエマツとピリカの中間のポコから降りている尾根を登ろうとその基部(上二股のこと)にアタックキャンプを構える。ここで一停滞のあと、この尾根の標高1340mにアタックキャンプを全身させる。翌日、ここからロングアタック。厳冬初登頂のソエマツ山頂から見た、神威岳の美しさに賛辞を惜しまない。この光景を見たのは、彼らが初めてだ。写真で見た上で登った僕らでさえ、息を呑む美しさだった。
「午後零時卅分、遂に神威の頂上に立つことができた。之でやつと來たんだ、私達は默つて互ひに祝福し合つた。ヤンチョ(橋本誠二氏)送る處のチヨコレートが取り出された。私達は未だ誰にも示されなかつた此處からの嚴な冬の景色を眺めて何故とはなしに嬉しかつた。此處に一つの足蹟を殘し得た事に無上の喜びを感じた。」結局十四時間行動。この時代の日高の未踏峰山行は、沢を詰め、最終キャンプから軽い身で10時間以上のロングアタックをかけて樹林帯に戻る。その典型的な形式である。何か潔い、知力と体力を尽くす登山スタイルだと思う。
以下は後半編に続く
●忠別川遡行 石橋恭一郎
● ヤオロマップ川遡行 豐田春滿
● 新しき山旅より
・ 音更川遡行 中村粂夫
・ 蘆別岳北尾根の池 鈴木限三
・ 散布岳 岡彦一
・ ペテガリ・ソナタ 有馬洋
・ 樺太の山雜感 岡彦一
・ 北部日高山脈の旅 山崎春雄
・ 一八二三米峰 中野龍雄
・ 蕃人 岡彦一
● 最近の十勝合宿について
ー冬期合宿覺え書きの一つとしてー 朝比奈英三
● 追悼
・懷舊 伊藤秀五郎
・ 伊藤周一君 福地文平
年報(1935/10−1938/4)
写真13点、スケッチ4点、地図3点
(解説前編/中編/後編)
- コメント (0)
OBの山行記録・ 2007年3月24日 (土)
 恒例の東京支部「スキーの宴」を、今年は松村会員(1959入部)の住む、那須で開催し、北は北海道から南は沖縄まで、全国から山とスキーを愛する老若男女の精鋭26名が集いました。三本槍岳へのスキー登山を行う者あり、中の大倉尾根で山スキーを楽しむ者あり、生まれて初めてスキーを経験する者ありで、世代を超えて親睦を図りました。
恒例の東京支部「スキーの宴」を、今年は松村会員(1959入部)の住む、那須で開催し、北は北海道から南は沖縄まで、全国から山とスキーを愛する老若男女の精鋭26名が集いました。三本槍岳へのスキー登山を行う者あり、中の大倉尾根で山スキーを楽しむ者あり、生まれて初めてスキーを経験する者ありで、世代を超えて親睦を図りました。【日程】 2007年3月16日(金)〜18日(日)
【場所】 那須・マウントジーンズスキー場(栃木県)
※宿泊は、麓のモンゴリアンビレッジテンゲルのゲル(パオ)。
【参加者】 26名、()内の数字は入部年
木村やし(1950)、○矢作(1952)、○石村(1953)+○ご夫人、坂野(1953)、○今村カケス(1956:小樽)+○娘さん、○岩崎(1956:宮城県)、*大森(1956:沖縄)、*川崎(1956:石川県)、○松村(1959:那須)、坂本(1959)、鶴巻(1959)+息子さん(高1)、○大村(1965)、*平田(1965)、浜名(1967)、◎*町田(1967)、◎*竹田(1968)、◎*古川(1970)、*毛利(1976)、*藤原(1980)+*息子さん(中3)+*娘さん(中2)、◎*清原(1986)、◎*山森(1986)
*印は3/17(土)からの参加者。
◎印は3/17(土)「三本槍岳スキー登山隊(5名、隊長:清原)」
○印は3/17(土)「中の大倉尾根:山スキーEnjoy隊(8名、隊長:大村)」
今年は全国的に暖冬で雪不足のため、果たしてこの時期(3月下旬)に那須で雪があるのかが心配でしたが、約1週間前に、強い寒気と冬型で恵みの雪が降り、20〜30cmの積雪があったとのことです。例年よりは雪は少ないものの、スキーを楽しむ分には必要十分な積雪があり、中の大倉尾根では、この時期では珍しいパウダースノーが楽しめるなど、充実した「スキーの宴」となりました。
以下に、「三本槍岳スキー登山隊(5名、清原隊長)」の記録を中心に報告します。
【ルート】
マウントジーンズスキー場=(中の大倉尾根)=三本槍岳
【行程】
3月17日(土)(小雪、上部強風)マウントジーンズスキー場ゴンドラ終点Co1410m(9:50)→Co1800ツエルト被って休憩(11:20-50)→Co1840mシーデポ(12:00)→三本槍岳1916.9m(12:40)→Co1840mシーデポ(13:15-30)→Co1440m休止中リフト終点(14:05-15)ーマウントジーンズスキー場ゴンドラ終点Co1410m(14:20)
【地図】 (五万図)那須岳、白河(二万五千)那須岳、那須湯本

3/17(土)の朝は、冬型の気圧配置ではあるもの、麓のモンゴリアンビレッジ付近からは、那須連峰全体を見渡すことができ、期待に胸が膨らむ。しかし、モンゴリアンビレッジで前日からの宿泊者と合流し、送迎バスでマウントジーンズスキー場に向かう頃には、那須連峰の上部はガスに覆われてしまった。

スキー場のフロントで、登山計画書を提出。ゴンドラ(1回券\1000-、50歳以上は\750-)の機動力を活用して、Co950mからCo1410mまで、標高差460mを、約10分で一気にあがる。ゴンドラ終点は小雪が舞っているものの、風はそんなに強くない。気温ー5℃。三本槍岳スキー登山隊、中の大倉尾根:山スキーEnjoy隊、ゲレンデスキーEnjoy隊の3隊合同で記念撮影。(今村カケスさんの娘さん撮影。)

中の大倉尾根下部を登る「三本槍岳スキー登山隊」。すぐ後ろには、「中の大倉尾根:山スキーEnjoy隊」が続いている。30歳前後もの年齢差がある大先輩の方々が、みなさん元気一杯に付いて来るのには、少々驚く。自分の30年後も、そうありたいと心から思う。

中の大倉尾根を登る、「中の大倉尾根:山スキーEnjoy隊」。

「三本槍岳スキー登山隊」が、Co1520m付近の森林限界で休憩していると、「中の大倉尾根:山スキーEnjoy隊」も到着した。小雪が舞う中、風も強くなってきて、この先は風を遮る樹林等がない。両隊が山の中で一緒だったのはここまで。「中の大倉尾根:山スキーEnjoy隊」は、このあと、傾斜が急になる手前のCo1700m付近までスキーで登り、引返したとのこと。

Co1700mからの急傾斜は、アイスバーンの上に粉雪が積もっており、シール登行しずらい。Co1800の赤面山への夏道分岐を過ぎたところで、ツエルトを被って30分の大休憩。コーヒーを沸かして飲む。おいしい。ツエルトの外はビンビラでも、薄っぺらい布を一枚被るだけで、暖かで、長時間休憩できるから不思議だ。実際にツエルトを被ってみて、冬山装備でのツエルトの重要性を一同で再認識する。

暖かいコーヒーを飲んで、体力を回復した我々は、視界のない強風の中、三本槍岳を目指して頑張って登る。Co1840mのスダレ山の南東の沢の源頭の雪が切れるところで、シーデポ。そこから先は、ツボ足で夏道を行く。風が強く、気温ー8℃。視界は200m前後か。目出帽を降ろす。春山のんびり山行のつもりが、冬山ビンビラ山行となった。

那須連峰の最高峰である三本槍岳(栃木・福島県境)への登頂を祝って硬い握手。山名の由来は、江戸時代に、会津藩・白河藩・黒羽藩の三藩が山頂に槍を建てて藩の境界にしたことによるらしい。天気も悪いので、記念撮影をして、すぐ引返す。写真は、左から、竹田、町田、古川、山森。(撮影:清原)

帰りは、登ってきた夏道を忠実に戻るだけだが、風でトレースも消えており、ところどころ夏道もはっきりせず、磁石を切ったりしながら戻る。

シーデポ(Co1840m)に無事戻り、滑降準備。

一瞬ガスが晴れて視界が利いたのを見逃さず、スダレ山の南東の沢の源頭をスキー滑降する。古川、竹田、町田の順に飛び出した。しかし、視界が利いたのは、ホンの一瞬だけであった。視界があれば笑いがとまらないほどスキーが快調であろう、スダレ山の南東の沢(=中の大倉尾根の北東側の沢)を、磁石を切ったりしながら、慎重に下り、Co1700m付近(尾根の傾斜の変わり目)で、中の大倉尾根の上に乗る。

中の大倉尾根を下るにつれて、視界が利いてきた。登っているときには、スキーを楽しむには傾斜が緩すぎるのでないかと思っていたが、そんなことはない。おいしいパウダーをいただきながらの快適なツリーランを楽しむ。風が強いせいか、先に引返した「中の大倉尾根:山スキーEnjoy隊(8名)」のトレースは完全に消えている。バージンスノーを楽しめる。写真は、最近、山板(カービング)と兼用靴を新調したという古川さんの滑り。

昔ながらの真っ直ぐな板と登山靴で、ツリーラン・パウダーランを楽しむ竹田さん(手前)と町田さん(後ろ)。竹田さんは、今時めずらしい革製の登山靴だ。私(山森)も2003年GWまでは革製の登山靴で山スキーを楽しんでいたが、カービング板と兼用靴を新調してからは、山でも、より上手に滑れるようになったので、ご参考まで(詳しくは、部報14号のp499〜503の記事参照)。ゲレンデでは、三本槍岳スキー登山隊、中の大倉尾根:山スキーEnjoy隊、ゲレンデスキーEnjoy隊の3隊が合流し、ゲレンデスキーを楽しんだり、休憩所で談笑したりして過ごす。

モンゴリアンビレッジテンゲルの露天風呂(温泉)で、お互いの隊の健闘を称え合う、「三本槍岳スキー登山隊」の清原隊長(1986入部、写真左)と、「中の大倉尾根:山スキーEnjoy隊」の大村隊長(1965年入部、写真右)。

モンゴリアンビレッジテンゲルの大食堂での夕食風景。

夕食後の、記念撮影。

ゲルの中での宴会の様子。今回の宿の選定に当たり、ご尽力いただいた那須在住の松村さん(1959入部)の、地元のご友人である平山さんも顔を出していただいた。今回の宿は、スキー場への送迎バスもあり、露天風呂(温泉)もあり、ゲル内で宴会もできて、大変良かったです。松村さん、平山さん、ありがとうございました。また、幹事の浜名さん、平田さんも、大変お疲れ様でした。

ゲルはこんな感じ。いくつかのゲルに分かれて泊まった。
3/18(日)は、ゲレンデに向かうものあり、疲れて帰宅するものありで、流れ解散となった。藤原さんの娘さん(中2)は、今回が生まれて初めてのスキー経験とのことで、今回の「スキーの宴」が、生涯の良い想い出となれば幸いです。
今回、最も若年の会員として参加した清原と私(山森)は、昨年(2006年1月22日(日))に、那須連峰・三本槍岳スキー登山の計画で現地入りするも、悪天候のため赤面山に行先を変更した経緯があり、そのリベンジを果たすことができ、大変満足しています。また、諸先輩方と交流を図ることができ、今後も、山スキーや沢登りに、是非ご一緒させていただきたく、今後の山登り人生にとって、大変有意義な「スキーの宴」参加であったと確信しています。皆様、ありがとうございました。
(報告:山森 聡)
◎印は3/17(土)「三本槍岳スキー登山隊(5名、隊長:清原)」
○印は3/17(土)「中の大倉尾根:山スキーEnjoy隊(8名、隊長:大村)」
今年は全国的に暖冬で雪不足のため、果たしてこの時期(3月下旬)に那須で雪があるのかが心配でしたが、約1週間前に、強い寒気と冬型で恵みの雪が降り、20〜30cmの積雪があったとのことです。例年よりは雪は少ないものの、スキーを楽しむ分には必要十分な積雪があり、中の大倉尾根では、この時期では珍しいパウダースノーが楽しめるなど、充実した「スキーの宴」となりました。
以下に、「三本槍岳スキー登山隊(5名、清原隊長)」の記録を中心に報告します。
【ルート】
マウントジーンズスキー場=(中の大倉尾根)=三本槍岳
【行程】
3月17日(土)(小雪、上部強風)マウントジーンズスキー場ゴンドラ終点Co1410m(9:50)→Co1800ツエルト被って休憩(11:20-50)→Co1840mシーデポ(12:00)→三本槍岳1916.9m(12:40)→Co1840mシーデポ(13:15-30)→Co1440m休止中リフト終点(14:05-15)ーマウントジーンズスキー場ゴンドラ終点Co1410m(14:20)
【地図】 (五万図)那須岳、白河(二万五千)那須岳、那須湯本

3/17(土)の朝は、冬型の気圧配置ではあるもの、麓のモンゴリアンビレッジ付近からは、那須連峰全体を見渡すことができ、期待に胸が膨らむ。しかし、モンゴリアンビレッジで前日からの宿泊者と合流し、送迎バスでマウントジーンズスキー場に向かう頃には、那須連峰の上部はガスに覆われてしまった。

スキー場のフロントで、登山計画書を提出。ゴンドラ(1回券\1000-、50歳以上は\750-)の機動力を活用して、Co950mからCo1410mまで、標高差460mを、約10分で一気にあがる。ゴンドラ終点は小雪が舞っているものの、風はそんなに強くない。気温ー5℃。三本槍岳スキー登山隊、中の大倉尾根:山スキーEnjoy隊、ゲレンデスキーEnjoy隊の3隊合同で記念撮影。(今村カケスさんの娘さん撮影。)

中の大倉尾根下部を登る「三本槍岳スキー登山隊」。すぐ後ろには、「中の大倉尾根:山スキーEnjoy隊」が続いている。30歳前後もの年齢差がある大先輩の方々が、みなさん元気一杯に付いて来るのには、少々驚く。自分の30年後も、そうありたいと心から思う。

中の大倉尾根を登る、「中の大倉尾根:山スキーEnjoy隊」。

「三本槍岳スキー登山隊」が、Co1520m付近の森林限界で休憩していると、「中の大倉尾根:山スキーEnjoy隊」も到着した。小雪が舞う中、風も強くなってきて、この先は風を遮る樹林等がない。両隊が山の中で一緒だったのはここまで。「中の大倉尾根:山スキーEnjoy隊」は、このあと、傾斜が急になる手前のCo1700m付近までスキーで登り、引返したとのこと。

Co1700mからの急傾斜は、アイスバーンの上に粉雪が積もっており、シール登行しずらい。Co1800の赤面山への夏道分岐を過ぎたところで、ツエルトを被って30分の大休憩。コーヒーを沸かして飲む。おいしい。ツエルトの外はビンビラでも、薄っぺらい布を一枚被るだけで、暖かで、長時間休憩できるから不思議だ。実際にツエルトを被ってみて、冬山装備でのツエルトの重要性を一同で再認識する。

暖かいコーヒーを飲んで、体力を回復した我々は、視界のない強風の中、三本槍岳を目指して頑張って登る。Co1840mのスダレ山の南東の沢の源頭の雪が切れるところで、シーデポ。そこから先は、ツボ足で夏道を行く。風が強く、気温ー8℃。視界は200m前後か。目出帽を降ろす。春山のんびり山行のつもりが、冬山ビンビラ山行となった。

那須連峰の最高峰である三本槍岳(栃木・福島県境)への登頂を祝って硬い握手。山名の由来は、江戸時代に、会津藩・白河藩・黒羽藩の三藩が山頂に槍を建てて藩の境界にしたことによるらしい。天気も悪いので、記念撮影をして、すぐ引返す。写真は、左から、竹田、町田、古川、山森。(撮影:清原)

帰りは、登ってきた夏道を忠実に戻るだけだが、風でトレースも消えており、ところどころ夏道もはっきりせず、磁石を切ったりしながら戻る。

シーデポ(Co1840m)に無事戻り、滑降準備。

一瞬ガスが晴れて視界が利いたのを見逃さず、スダレ山の南東の沢の源頭をスキー滑降する。古川、竹田、町田の順に飛び出した。しかし、視界が利いたのは、ホンの一瞬だけであった。視界があれば笑いがとまらないほどスキーが快調であろう、スダレ山の南東の沢(=中の大倉尾根の北東側の沢)を、磁石を切ったりしながら、慎重に下り、Co1700m付近(尾根の傾斜の変わり目)で、中の大倉尾根の上に乗る。

中の大倉尾根を下るにつれて、視界が利いてきた。登っているときには、スキーを楽しむには傾斜が緩すぎるのでないかと思っていたが、そんなことはない。おいしいパウダーをいただきながらの快適なツリーランを楽しむ。風が強いせいか、先に引返した「中の大倉尾根:山スキーEnjoy隊(8名)」のトレースは完全に消えている。バージンスノーを楽しめる。写真は、最近、山板(カービング)と兼用靴を新調したという古川さんの滑り。

昔ながらの真っ直ぐな板と登山靴で、ツリーラン・パウダーランを楽しむ竹田さん(手前)と町田さん(後ろ)。竹田さんは、今時めずらしい革製の登山靴だ。私(山森)も2003年GWまでは革製の登山靴で山スキーを楽しんでいたが、カービング板と兼用靴を新調してからは、山でも、より上手に滑れるようになったので、ご参考まで(詳しくは、部報14号のp499〜503の記事参照)。ゲレンデでは、三本槍岳スキー登山隊、中の大倉尾根:山スキーEnjoy隊、ゲレンデスキーEnjoy隊の3隊が合流し、ゲレンデスキーを楽しんだり、休憩所で談笑したりして過ごす。

モンゴリアンビレッジテンゲルの露天風呂(温泉)で、お互いの隊の健闘を称え合う、「三本槍岳スキー登山隊」の清原隊長(1986入部、写真左)と、「中の大倉尾根:山スキーEnjoy隊」の大村隊長(1965年入部、写真右)。

モンゴリアンビレッジテンゲルの大食堂での夕食風景。

夕食後の、記念撮影。

ゲルの中での宴会の様子。今回の宿の選定に当たり、ご尽力いただいた那須在住の松村さん(1959入部)の、地元のご友人である平山さんも顔を出していただいた。今回の宿は、スキー場への送迎バスもあり、露天風呂(温泉)もあり、ゲル内で宴会もできて、大変良かったです。松村さん、平山さん、ありがとうございました。また、幹事の浜名さん、平田さんも、大変お疲れ様でした。

ゲルはこんな感じ。いくつかのゲルに分かれて泊まった。
3/18(日)は、ゲレンデに向かうものあり、疲れて帰宅するものありで、流れ解散となった。藤原さんの娘さん(中2)は、今回が生まれて初めてのスキー経験とのことで、今回の「スキーの宴」が、生涯の良い想い出となれば幸いです。
今回、最も若年の会員として参加した清原と私(山森)は、昨年(2006年1月22日(日))に、那須連峰・三本槍岳スキー登山の計画で現地入りするも、悪天候のため赤面山に行先を変更した経緯があり、そのリベンジを果たすことができ、大変満足しています。また、諸先輩方と交流を図ることができ、今後も、山スキーや沢登りに、是非ご一緒させていただきたく、今後の山登り人生にとって、大変有意義な「スキーの宴」参加であったと確信しています。皆様、ありがとうございました。
(報告:山森 聡)
- コメント (1)
OBの山行記録・ 2007年3月14日 (水)

【年月日】 平成19年2月25日
【メンバ】清野(76年入部)、真庭(沼田山岳会)
【ルート】 一ノ倉一ノ沢左方ルンゼ〜一、二ノ沢中間稜〜東尾根〜谷川岳山頂
【時 間】指導センター(03:30)一ノ倉出合(04:20)左方ルンゼ(06:30)山頂(15:00)
三峰川の源流で、対岸の尾根の熊を睨みながら、雪崩にやられるのと熊に食われるのはどちらが良いかなどと考えながら、救出のヘリを待っていた時から早一年、ようやくホンチャン復帰ができました。
例年であれば、巨大なブロックで埋め尽くされている一ノ倉出合も、沢の水が汲める程雪がありませんでした。
急雪壁やラビーネンツークを登る部分が多い谷川のルンゼルートも、今年は氷の露出が多く、ラッセルやキノコ雪、ブロック崩壊に悩まされる事も少なく、快適な登攀が楽しめました。
左方ルンゼの上部左岸にメガネと言われる大きな風穴があります。
満月の夜、窓岩(赤岩)のふちに座って笛を吹いた矢野先輩の向こうを張って、此処で笛でも吹こうと思ったのですが......とてもそのような事ができる場所ではありませんでした。

左方ルンゼ取付 積雪が少ないため、滝が例年より10m程高い

F2

核心部 F5 チムニー滝 抜け口の氷が薄くて少々シビアー、おまけにスノーシャワーの洗礼を受ける

F5を抜け上部草付帯を望む

メガネ(風穴)から見下ろす一ノ倉出合 満月の夜に、此処で笛を吹こうと思っていたが、底は急傾斜で一ノ沢に向かって落ち込んでいる、チョット無理かな!?

奥壁と一ノ倉岳

一、二ノ沢中間稜を行く 狭苦しいルンゼから解放され、快適なナイフリッジを行く
例年であれば、巨大なブロックで埋め尽くされている一ノ倉出合も、沢の水が汲める程雪がありませんでした。
急雪壁やラビーネンツークを登る部分が多い谷川のルンゼルートも、今年は氷の露出が多く、ラッセルやキノコ雪、ブロック崩壊に悩まされる事も少なく、快適な登攀が楽しめました。
左方ルンゼの上部左岸にメガネと言われる大きな風穴があります。
満月の夜、窓岩(赤岩)のふちに座って笛を吹いた矢野先輩の向こうを張って、此処で笛でも吹こうと思ったのですが......とてもそのような事ができる場所ではありませんでした。

左方ルンゼ取付 積雪が少ないため、滝が例年より10m程高い

F2

核心部 F5 チムニー滝 抜け口の氷が薄くて少々シビアー、おまけにスノーシャワーの洗礼を受ける

F5を抜け上部草付帯を望む

メガネ(風穴)から見下ろす一ノ倉出合 満月の夜に、此処で笛を吹こうと思っていたが、底は急傾斜で一ノ沢に向かって落ち込んでいる、チョット無理かな!?

奥壁と一ノ倉岳

一、二ノ沢中間稜を行く 狭苦しいルンゼから解放され、快適なナイフリッジを行く
- コメント (1)
OBの山行記録・ 2007年3月6日 (火)
三田原山(2347m)の南端Co2300m、前山(1920m)

●2007年2月17日(土)(1ー0)
【ルート】
妙高国際スキー場→三田原山(2347m)の南端Co2300m→(北東面滑降)→南地獄谷→前山→(滝沢尾根滑降)→赤倉観光ホテルスキー場下部
【メンバ】
L:石橋岳志(1982入部)、M:松木博文(1983入部)、山森聡(1986入部)

●2007年2月17日(土)(1ー0)
【ルート】
妙高国際スキー場→三田原山(2347m)の南端Co2300m→(北東面滑降)→南地獄谷→前山→(滝沢尾根滑降)→赤倉観光ホテルスキー場下部
【メンバ】
L:石橋岳志(1982入部)、M:松木博文(1983入部)、山森聡(1986入部)
【行程】
2月17日(土)(晴れ)妙高国際スキー場リフト終点Co1850m(8:45)→三田原山(2347m)の南端Co2300m(10:30-11:00)→南地獄谷(大谷ヒュッテ付近)Co1800m(11:50-12:10)→前山1920m(13:10-35)→滝沢尾根Co1000付近渡渉点(14:40-50)→赤倉観光ホテルスキー場Co1000m付近(15:00-10)→Co730m駐車場(15:20)
【地図】 (五万図)妙高山
【記録】
新潟県妙高市の松木邸(1983入部)をベースに、1日目は妙高(三田原山〜前山)、2日目は黒姫山に行く計画を立てた。当初は清原ババアも同行する予定であったが、家庭の事情でどうしても都合がつかなくなってしまい、石橋兄、松木、山森の3名での山行となった。

東京を早朝出発し、赤倉観光ホテルスキー場の駐車場(下山口)で、地元の松木さんと7:00に集合。写真は、駐車場から望む妙高連峰。左から赤倉山、(南地獄谷)、妙高山(手前が前山)、(北地獄谷)、神奈山である。天気は良く、気分も最高。松木号は集合場所(下山口)にデポし、山森号に乗り換えて、妙高国際スキー場(登山口)へと向かう。

妙高国際スキー場では、杉の原ゴンドラ(1250m,11分,1回券\1000-)と、三田原第3高速リフト(1726m,7分,1回券\500-)の起動力を活用して、Co1850mまで標高差1000m以上を楽をして上がることができる。ゴンドラを降りて、スキー場を快調に滑って、三田原第3高速リフトの乗り場には8:00位に到着したが、リフトがまだ動いていない。しばらく景色を眺めながら待つこととする。下界には雲海が広がり、なかなか幻想的で美しい(写真)。8:30頃には、リフトが動き出した。

リフト終点からは、三田原山の外輪山を目指して、トラバース気味にスキーで登って行く。この日は我々が一番乗りだが、過去のトレースも残っている。歩き出してすぐ、沢型をひとつ越える(写真)。

翌日に行く予定の黒姫山(写真)を左に見ながら登る。途中で、アイスバーンのところがあって、スキーアイゼンを持っている私以外は、シートラして壷足で蹴りこんで登ることにより、アイスバーンを通過する。

乙妻山や北アルプスの山々を背に、三田原山(妙高山の外輪山)を目指して登る山森(写真)。本当に景色が素晴らしい。この斜面もスキーは快調そうだが、南面のため、雪質は、あまり良くない。今回の計画では、三田原山からは北面のパウダー、前山からは樹林帯のパウダーをいただく予定である。期待に胸をふくらませつつ登る。

三田原山(外輪山の南端Co2300m付近)に到着した松木さん(左)と山森(右)。バックは妙高山(2445.9m)。三田原山の最高点(2347m)まではもう少し、外輪山を北に歩く必要があるが、スキー滑降が目的の我々は、計画通り、ここまでとする。

山スキーとスノーボードの若者2人組が、到着したので、北アルプスをバックに写真を撮ってもらう。左から、山森、松木、石橋兄。彼らは、休憩した後、三田原山の最高点(2347m)を目指して歩いていった。スノーボードは、真ん中から2つに割れるタイプで、シールをつけて山スキーのように足につけて歩いて登れるタイプだった。話には聞いたことがあったが、実物は初めて見た。

三田原山から、黒姫山、佐渡山、高妻山、乙妻山を望む。黒姫山の左手に富士山も見えた。

三田原山から、北アルプスの山々を望む。乙妻山の右上には、遠く、槍ヶ岳も見える。写真中央には、剣岳も見えている。

外輪山の内側に向かって滑り込む。北斜面なので、期待通りのパウダーだ。写真はテレマークの石橋兄。

こんな急斜面も、気持ち良く滑れるようになった私(山森)。ゲレンデでスキー技術を磨くと、雪山での楽しさが何倍、何十倍にもなる。本当に!

山スキーは、2003年GWの火打山&焼山北面スキー山行(斎藤、松木、山森、銭谷)以来だという松木さんも、地元の意地で、なかなかの滑り。

外輪山の急斜面を滑り降りたあとは、南地獄谷の緩い傾斜を滑っていく。地図の温泉記号(Co1920m)は、沢が口を空けており、煙がもくもくと立っている(写真)。左岸側を滑り降りるが、崖などに注意しながら、緊張して降りる。

南地獄谷(大谷ヒュッテ付近)Co1800mからは、またシールをつけて、前山(1920m)に向けて登る。前山から妙高山への尾根は、細くてアップダウンが多くブッシュも鬱陶しいので、スキーでの通過は不快調との情報があり、少し憂鬱であった。しかし、現地でのルートファインディングの結果、尾根にはあがらずに、尾根の南側をトラバースしながら登って行き、前山ピーク直前で尾根上にでることができた。前山は眺望が素晴らしい(写真)。

前山から望む、越後三山方面。尾瀬の燧ケ岳や至仏山も見える。この日は、八ヶ岳、富士山、南アルプス、中央アルプス、北アルプスまで、ばっちりと見えていたので、数えてはいないが、日本百名山の半分以上が見えていたのではないだろうか?

松木さんのスキーは、昔ながらの真っ直ぐな板に、金具はジルブレッタ300。靴はプラスチック登山靴。ジャンパーは、秀岳荘のナイロンジャンパー。現役時代の装備かと思って聞いたら、ジャンパー以外は、卒業してから新調したんだそうだ。そろそろ、買い替え時ですよ。松木さん! 高橋GGさん(1984入部)も、今年、一式新調したみたいだし...

前山から、滝沢尾根への下りは、最初は少々細いが、ところどころパウダーのたまっている斜面を、気持ちよく滑る。写真は松木さん。

なかなか格好良く写真を撮ってくれてありがとう。撮影:石橋兄、モデル:山森。この滝沢尾根は、例年より2m位雪が少ないそうだ。例年なら、写真のブッシュも全て雪の下で、快適な大斜面なのだろう。しかし、湯ノ丸山で、最強のブッシュスキーを経験済みなので、少々の潅木は気にならない。

快調なツリーランを楽しむ石橋兄。樹林帯はパウダースノーが楽しめる。

Co1000m付近の渡渉点は、笹を掴みながら横滑りで降りて、シールをつけて、何とか残っているスノーブリッジを利用して渡渉。例年の雪なら何でもないのだろうが、雪不足の今年は、ちょっと不快調。渡渉したあとは、左岸のブル道をほぼ同コンタで歩いていくと、赤倉観光ホテルスキー場の下部に出る。ゲレンデを滑って、無事下山。三田原山から先は、他のパーティに会うこともなく、晴天のもと、静かなスキー山行を楽しむことができた。

松木号で、妙高国際スキー場(登山口)へ行って、山森号を回収。お決まりの温泉は、妙高市営の妙高高原ふれあい会館(\450-)。

松木邸では、松木さんの家族も加わり、大宴会。自家製の手打ちそばもごちそうになる。あたたかい布団でぐっすりと眠らせてもらう。翌日は、あいにくの雨のため、黒姫山への山行は中止とする。地元の山岳会で山スキーに登攀に活躍しているという松木さんのお姉さん宅を訪問し、楽しい話を聞かせてもらい、東京へ帰った。これからも、年1回位は、松木家にお世話になって、頚城山塊の山スキーを楽しむことにしよう。
(文責:山森 聡)
2月17日(土)(晴れ)妙高国際スキー場リフト終点Co1850m(8:45)→三田原山(2347m)の南端Co2300m(10:30-11:00)→南地獄谷(大谷ヒュッテ付近)Co1800m(11:50-12:10)→前山1920m(13:10-35)→滝沢尾根Co1000付近渡渉点(14:40-50)→赤倉観光ホテルスキー場Co1000m付近(15:00-10)→Co730m駐車場(15:20)
【地図】 (五万図)妙高山
【記録】
新潟県妙高市の松木邸(1983入部)をベースに、1日目は妙高(三田原山〜前山)、2日目は黒姫山に行く計画を立てた。当初は清原ババアも同行する予定であったが、家庭の事情でどうしても都合がつかなくなってしまい、石橋兄、松木、山森の3名での山行となった。

東京を早朝出発し、赤倉観光ホテルスキー場の駐車場(下山口)で、地元の松木さんと7:00に集合。写真は、駐車場から望む妙高連峰。左から赤倉山、(南地獄谷)、妙高山(手前が前山)、(北地獄谷)、神奈山である。天気は良く、気分も最高。松木号は集合場所(下山口)にデポし、山森号に乗り換えて、妙高国際スキー場(登山口)へと向かう。

妙高国際スキー場では、杉の原ゴンドラ(1250m,11分,1回券\1000-)と、三田原第3高速リフト(1726m,7分,1回券\500-)の起動力を活用して、Co1850mまで標高差1000m以上を楽をして上がることができる。ゴンドラを降りて、スキー場を快調に滑って、三田原第3高速リフトの乗り場には8:00位に到着したが、リフトがまだ動いていない。しばらく景色を眺めながら待つこととする。下界には雲海が広がり、なかなか幻想的で美しい(写真)。8:30頃には、リフトが動き出した。

リフト終点からは、三田原山の外輪山を目指して、トラバース気味にスキーで登って行く。この日は我々が一番乗りだが、過去のトレースも残っている。歩き出してすぐ、沢型をひとつ越える(写真)。

翌日に行く予定の黒姫山(写真)を左に見ながら登る。途中で、アイスバーンのところがあって、スキーアイゼンを持っている私以外は、シートラして壷足で蹴りこんで登ることにより、アイスバーンを通過する。

乙妻山や北アルプスの山々を背に、三田原山(妙高山の外輪山)を目指して登る山森(写真)。本当に景色が素晴らしい。この斜面もスキーは快調そうだが、南面のため、雪質は、あまり良くない。今回の計画では、三田原山からは北面のパウダー、前山からは樹林帯のパウダーをいただく予定である。期待に胸をふくらませつつ登る。

三田原山(外輪山の南端Co2300m付近)に到着した松木さん(左)と山森(右)。バックは妙高山(2445.9m)。三田原山の最高点(2347m)まではもう少し、外輪山を北に歩く必要があるが、スキー滑降が目的の我々は、計画通り、ここまでとする。

山スキーとスノーボードの若者2人組が、到着したので、北アルプスをバックに写真を撮ってもらう。左から、山森、松木、石橋兄。彼らは、休憩した後、三田原山の最高点(2347m)を目指して歩いていった。スノーボードは、真ん中から2つに割れるタイプで、シールをつけて山スキーのように足につけて歩いて登れるタイプだった。話には聞いたことがあったが、実物は初めて見た。
三田原山から、黒姫山、佐渡山、高妻山、乙妻山を望む。黒姫山の左手に富士山も見えた。
三田原山から、北アルプスの山々を望む。乙妻山の右上には、遠く、槍ヶ岳も見える。写真中央には、剣岳も見えている。

外輪山の内側に向かって滑り込む。北斜面なので、期待通りのパウダーだ。写真はテレマークの石橋兄。

こんな急斜面も、気持ち良く滑れるようになった私(山森)。ゲレンデでスキー技術を磨くと、雪山での楽しさが何倍、何十倍にもなる。本当に!

山スキーは、2003年GWの火打山&焼山北面スキー山行(斎藤、松木、山森、銭谷)以来だという松木さんも、地元の意地で、なかなかの滑り。

外輪山の急斜面を滑り降りたあとは、南地獄谷の緩い傾斜を滑っていく。地図の温泉記号(Co1920m)は、沢が口を空けており、煙がもくもくと立っている(写真)。左岸側を滑り降りるが、崖などに注意しながら、緊張して降りる。

南地獄谷(大谷ヒュッテ付近)Co1800mからは、またシールをつけて、前山(1920m)に向けて登る。前山から妙高山への尾根は、細くてアップダウンが多くブッシュも鬱陶しいので、スキーでの通過は不快調との情報があり、少し憂鬱であった。しかし、現地でのルートファインディングの結果、尾根にはあがらずに、尾根の南側をトラバースしながら登って行き、前山ピーク直前で尾根上にでることができた。前山は眺望が素晴らしい(写真)。
前山から望む、越後三山方面。尾瀬の燧ケ岳や至仏山も見える。この日は、八ヶ岳、富士山、南アルプス、中央アルプス、北アルプスまで、ばっちりと見えていたので、数えてはいないが、日本百名山の半分以上が見えていたのではないだろうか?

松木さんのスキーは、昔ながらの真っ直ぐな板に、金具はジルブレッタ300。靴はプラスチック登山靴。ジャンパーは、秀岳荘のナイロンジャンパー。現役時代の装備かと思って聞いたら、ジャンパー以外は、卒業してから新調したんだそうだ。そろそろ、買い替え時ですよ。松木さん! 高橋GGさん(1984入部)も、今年、一式新調したみたいだし...

前山から、滝沢尾根への下りは、最初は少々細いが、ところどころパウダーのたまっている斜面を、気持ちよく滑る。写真は松木さん。

なかなか格好良く写真を撮ってくれてありがとう。撮影:石橋兄、モデル:山森。この滝沢尾根は、例年より2m位雪が少ないそうだ。例年なら、写真のブッシュも全て雪の下で、快適な大斜面なのだろう。しかし、湯ノ丸山で、最強のブッシュスキーを経験済みなので、少々の潅木は気にならない。

快調なツリーランを楽しむ石橋兄。樹林帯はパウダースノーが楽しめる。

Co1000m付近の渡渉点は、笹を掴みながら横滑りで降りて、シールをつけて、何とか残っているスノーブリッジを利用して渡渉。例年の雪なら何でもないのだろうが、雪不足の今年は、ちょっと不快調。渡渉したあとは、左岸のブル道をほぼ同コンタで歩いていくと、赤倉観光ホテルスキー場の下部に出る。ゲレンデを滑って、無事下山。三田原山から先は、他のパーティに会うこともなく、晴天のもと、静かなスキー山行を楽しむことができた。

松木号で、妙高国際スキー場(登山口)へ行って、山森号を回収。お決まりの温泉は、妙高市営の妙高高原ふれあい会館(\450-)。

松木邸では、松木さんの家族も加わり、大宴会。自家製の手打ちそばもごちそうになる。あたたかい布団でぐっすりと眠らせてもらう。翌日は、あいにくの雨のため、黒姫山への山行は中止とする。地元の山岳会で山スキーに登攀に活躍しているという松木さんのお姉さん宅を訪問し、楽しい話を聞かせてもらい、東京へ帰った。これからも、年1回位は、松木家にお世話になって、頚城山塊の山スキーを楽しむことにしよう。
(文責:山森 聡)
- コメント (1)
OBの山行記録・ 2007年3月6日 (火)
一切経山(1948.8m)のコル(Co1900m)、高山(1804.8m)

●2007年2月3日(土)〜4日(日)(2ー0)
【ルート】
高湯→賽河原→KO山荘分岐→五色沼→一切経山コル→酸ガ平→浄土平→吾妻小舎C1→鳥子平→高山→土湯
【メンバ】
L:石橋岳志(1982入部)、M:山森聡(1986入部)、清原実(1986入部)、銭谷竜一(1990入部)

●2007年2月3日(土)〜4日(日)(2ー0)
【ルート】
高湯→賽河原→KO山荘分岐→五色沼→一切経山コル→酸ガ平→浄土平→吾妻小舎C1→鳥子平→高山→土湯
【メンバ】
L:石橋岳志(1982入部)、M:山森聡(1986入部)、清原実(1986入部)、銭谷竜一(1990入部)
【行程】
2月3日(土)(晴れ)高湯Co830m(8:15)→スカイラインCo1140m(9:20-30)→KO山荘分岐Co1550m(12:10-20)→五色沼北東Co1800mポコ(強風、13:50)→五色沼西側Co1780m(14:30)→一切経山コル滑り出しCo1860(15:30)→吾妻小舎Co1580m C1(16:40)
2月4日(日)(吹雪)吾妻小舎C1(7:20)→スカイライン(7:30)→鳥子平(スカイライン最高点)Co1620m(8:20-30)→高山1804.8m(10:00)→Co1740m付近滑降開始(10:20)→1024.7mポコ北側(12:40)→林道Co700付近休憩(13:20)→除雪車道Co550(14:10-20)→土湯(14:40)
※2日目に東吾妻山(1974.7m)にも行く計画であったが、悪天候(吹雪)のため断念。
【地図】 (五万図)吾妻山、福島
【記録】
東京組の3人(石橋兄、清原、山森)と、仙台在住の銭谷の計4人で、1泊2日で、東北・東吾妻スキー山行を楽しんできた。

<1日目>
東京、仙台をそれぞれ早朝に出発し、福島西ICに6:00集合。土湯(下山口)に、銭谷号をデポし、石橋兄号で高湯(登山口)に向かう。土湯から高湯へ向かう車窓からは、今回行く東吾妻が良く見えた。高湯の吾妻スキー場は今年から営業を休止してしまっている。リフトの機動力が使えないので、吾妻小舎までは、昨年までと比べて、3時間位、余計に歩かないと到達できない。ゲレンデ跡ではなく、夏道沿いにシールで登高することにする。

古いスキーツアーの標識が、樹木に食い込んでいる。家形ヒュッテというのは、1952年に開設され、1970年頃に雪崩で半壊、1974年には解体された山小屋らしい。このことから、1960年代の標識であろうと想像できる。約40年かけて樹木が成長して、このように標識が食い込んでしまったのだろう。

福島平野をバックに、ブッシュの鬱陶しい夏道をラッセルして進む。登山口で出会ったKO山荘の管理人さんの話によると、今年は極端に雪が少なく、例年の3分の1以下の積雪量とのことであった。

KO山荘分岐近くで見かけた、古いスキーツアーの標識。ニッポンビールと書いてある。サッポロビールのホームページによると、日本麦酒(ニッポンビール)から、サッポロビールへの社名変更が、1964年1月とのことなので、少なくとも43年以上昔に設置された標識だと思われる。ちなみに私の地図では「KO山荘」となっているが、新しい版だと「慶應吾妻山荘」と書いてあるようだ。私は、KOはノックアウトのことだったりしてと想像を膨らましていたが、どうやら慶応義塾大学の関係の山荘のようだ。

Co1750mで尾根に上がったところ。景色が良い。(写真は石橋兄)

五色沼北東Co1800mポコに上がると、立っているがやっとの強風。この強風ではここで撤退かとも考えたが、石橋兄が空身で、五色沼の北側まで偵察に行ってみたところ、強風はポコ周辺の局地的なものと判明。スキーを手で持って、風がないところまで、皆で降りて前進する。(写真は銭谷)

五色沼西側Co1780mで大休止。凍結した五色沼の左(北)には家形山(1880m)、右(南)には一切経山(1948.8m)が聳え立ち、なかなか美しい景色で、見ていて飽きない。

一切経山のコルへの登高中に、家形山や五色沼方面を振り返る。

一切経山のコル周辺は、視界がないとシビアな地形だ。

一切経山のコルにて記念撮影。本日の最高地点である(Co1900m)。ここからは、前大巓とのコル方面に回りこんでから、シールを外して酸ヶ平へスキー滑降。

酸ヶ平も、視界がないとシビアな地形だ。地図で現在地と吾妻小舎へのルートを確認し、メンバ同士でお互いに確認し合う。

酸ヶ平から浄土平への下り(前半)は、斜度もあり、スキーが快調だ。写真はテレマークの石橋兄。

酸ヶ平から浄土平への下り(後半)は、斜度が緩くなり、正面に吾妻小富士を見ながらのスキー滑降となる。写真は、吾妻小富士に向かって軽快なショートターンで滑る清原ババア。吾妻富士の右側の黒い台地(桶沼)の裏側が、本日の目的地の吾妻小舎だ。浄土平から桶沼の裏への回りこみは、再度シールをつけて歩いた。

吾妻小舎は、昨年までは冬でも週末は管理人の方が入っていたそうだが、今年から吾妻スキー場が営業を休止したことから、管理人の方は入らないとのこと。事前に連絡し、素泊まり4800円/人+燃料費は別途支払って、泊めさせてもらった。布団もあるので、装備はほとんど日帰り装備だ。夕食は、キムチ鍋とうどんを作って食べた。山で食うメシはうまい!

石炭ストーブなのだが、つけ方の要領が良くわからず、つくまでに相当苦労した。石橋兄が入部したときは、ヘルベチアヒュッテが「石炭ストーブ」だったそうだが、あとの3人が入部した時は、ヘルベチアヒュッテも空沼小屋も「蒔ストーブ」だったので、石炭ストーブをつけた経験がないのだ。十勝での冬合宿の白銀荘は石炭ストーブだったが、夜のストーブ番はしても、消えているストーブをつけたことはなかったと思う。

<2日目>
夜中から雪が降り続き、翌朝は40cm位、新たに積雪があった。ゾンデ棒での測定で、積雪240cm位。天気は雪。当初計画では、東吾妻山(1974.7m)へも行く予定であったが、悪天候なので断念。直接、高山(1804.8m)へ向かうことにする。高山はピークまで樹林帯なので、吹雪で視界がなくても、何とか乗っ越せるであろうと判断した。

悪天候(雪)の磐梯吾妻スカイラインを、ラッセルを交代しながら道路の最高点(鳥子平)まで進む。

鳥子平から高山への登り。ラッセルが深いので交代しながら頑張って登る。ピーク直下はブッシュが鬱陶しい。

吹雪の高山ピークにて。ピークには電波の反射板が設置されており、ちょっと興ざめ。とにかく風が強いので、シールをつけたまま、風の当たらないところまで南側に降りてから、休憩。

休憩していたら、外国人をリーダとする5人パーティが後ろからやってきた。西吾妻からテント泊3泊4日で縦走してきたという。この日は、我々のトレースを辿って来たという。バージンスノーをいただくために、休憩もそこそこに、我々は滑降を開始した。雪が深いが、傾斜があるところでは、なかなかパウダースキーを堪能できる。快感!

思っていたほどブッシュも鬱陶しくなく、快適なツリーランを楽しむ。ただ、後半は斜度が緩いため、先頭の人はスキーが滑らないので歩く必要があるが、2番目以降の人は、トレース上に立っているだけで、滑っていける。皆で、先頭を譲りあいながら、下る。そうこうしていると、5人パーティが追いついてきて、抜きつ抜かれつしながら下山する。

1024.7mのポコは北側を捲いて、夏道に乗る。この先の夏道は、林道のように大きく切り開かれているので、写真のように、スキーは快調だ。

林道は先頭の人は滑らないが、2番目以降の人はトレース上なら滑るという微妙な傾斜。5人組パーティも含めて、先頭を譲り合いながら下る。長い林道だ。途中、男沼を眺めながら休憩(写真)。

銭谷号に2人乗り、高湯の石橋兄号の回収に行ってもらう。その間、留守番の2人(清原、山森)で、地元福島出身の札幌の斎藤(1987入部)に電話して、土湯での、おすすめの温泉等を紹介してもらう。その結果、お決まりの温泉は、斎藤のいとこの家である「ニュー扇屋」。湯上りには、自家製の「森山の温泉卵」をごちそうになる。とてもおいしい。皆、お土産に「森山の温泉卵」を買って帰った。
(文責:山森 聡)
2月3日(土)(晴れ)高湯Co830m(8:15)→スカイラインCo1140m(9:20-30)→KO山荘分岐Co1550m(12:10-20)→五色沼北東Co1800mポコ(強風、13:50)→五色沼西側Co1780m(14:30)→一切経山コル滑り出しCo1860(15:30)→吾妻小舎Co1580m C1(16:40)
2月4日(日)(吹雪)吾妻小舎C1(7:20)→スカイライン(7:30)→鳥子平(スカイライン最高点)Co1620m(8:20-30)→高山1804.8m(10:00)→Co1740m付近滑降開始(10:20)→1024.7mポコ北側(12:40)→林道Co700付近休憩(13:20)→除雪車道Co550(14:10-20)→土湯(14:40)
※2日目に東吾妻山(1974.7m)にも行く計画であったが、悪天候(吹雪)のため断念。
【地図】 (五万図)吾妻山、福島
【記録】
東京組の3人(石橋兄、清原、山森)と、仙台在住の銭谷の計4人で、1泊2日で、東北・東吾妻スキー山行を楽しんできた。

<1日目>
東京、仙台をそれぞれ早朝に出発し、福島西ICに6:00集合。土湯(下山口)に、銭谷号をデポし、石橋兄号で高湯(登山口)に向かう。土湯から高湯へ向かう車窓からは、今回行く東吾妻が良く見えた。高湯の吾妻スキー場は今年から営業を休止してしまっている。リフトの機動力が使えないので、吾妻小舎までは、昨年までと比べて、3時間位、余計に歩かないと到達できない。ゲレンデ跡ではなく、夏道沿いにシールで登高することにする。

古いスキーツアーの標識が、樹木に食い込んでいる。家形ヒュッテというのは、1952年に開設され、1970年頃に雪崩で半壊、1974年には解体された山小屋らしい。このことから、1960年代の標識であろうと想像できる。約40年かけて樹木が成長して、このように標識が食い込んでしまったのだろう。

福島平野をバックに、ブッシュの鬱陶しい夏道をラッセルして進む。登山口で出会ったKO山荘の管理人さんの話によると、今年は極端に雪が少なく、例年の3分の1以下の積雪量とのことであった。

KO山荘分岐近くで見かけた、古いスキーツアーの標識。ニッポンビールと書いてある。サッポロビールのホームページによると、日本麦酒(ニッポンビール)から、サッポロビールへの社名変更が、1964年1月とのことなので、少なくとも43年以上昔に設置された標識だと思われる。ちなみに私の地図では「KO山荘」となっているが、新しい版だと「慶應吾妻山荘」と書いてあるようだ。私は、KOはノックアウトのことだったりしてと想像を膨らましていたが、どうやら慶応義塾大学の関係の山荘のようだ。

Co1750mで尾根に上がったところ。景色が良い。(写真は石橋兄)

五色沼北東Co1800mポコに上がると、立っているがやっとの強風。この強風ではここで撤退かとも考えたが、石橋兄が空身で、五色沼の北側まで偵察に行ってみたところ、強風はポコ周辺の局地的なものと判明。スキーを手で持って、風がないところまで、皆で降りて前進する。(写真は銭谷)

五色沼西側Co1780mで大休止。凍結した五色沼の左(北)には家形山(1880m)、右(南)には一切経山(1948.8m)が聳え立ち、なかなか美しい景色で、見ていて飽きない。
一切経山のコルへの登高中に、家形山や五色沼方面を振り返る。

一切経山のコル周辺は、視界がないとシビアな地形だ。

一切経山のコルにて記念撮影。本日の最高地点である(Co1900m)。ここからは、前大巓とのコル方面に回りこんでから、シールを外して酸ヶ平へスキー滑降。

酸ヶ平も、視界がないとシビアな地形だ。地図で現在地と吾妻小舎へのルートを確認し、メンバ同士でお互いに確認し合う。

酸ヶ平から浄土平への下り(前半)は、斜度もあり、スキーが快調だ。写真はテレマークの石橋兄。

酸ヶ平から浄土平への下り(後半)は、斜度が緩くなり、正面に吾妻小富士を見ながらのスキー滑降となる。写真は、吾妻小富士に向かって軽快なショートターンで滑る清原ババア。吾妻富士の右側の黒い台地(桶沼)の裏側が、本日の目的地の吾妻小舎だ。浄土平から桶沼の裏への回りこみは、再度シールをつけて歩いた。

吾妻小舎は、昨年までは冬でも週末は管理人の方が入っていたそうだが、今年から吾妻スキー場が営業を休止したことから、管理人の方は入らないとのこと。事前に連絡し、素泊まり4800円/人+燃料費は別途支払って、泊めさせてもらった。布団もあるので、装備はほとんど日帰り装備だ。夕食は、キムチ鍋とうどんを作って食べた。山で食うメシはうまい!

石炭ストーブなのだが、つけ方の要領が良くわからず、つくまでに相当苦労した。石橋兄が入部したときは、ヘルベチアヒュッテが「石炭ストーブ」だったそうだが、あとの3人が入部した時は、ヘルベチアヒュッテも空沼小屋も「蒔ストーブ」だったので、石炭ストーブをつけた経験がないのだ。十勝での冬合宿の白銀荘は石炭ストーブだったが、夜のストーブ番はしても、消えているストーブをつけたことはなかったと思う。

<2日目>
夜中から雪が降り続き、翌朝は40cm位、新たに積雪があった。ゾンデ棒での測定で、積雪240cm位。天気は雪。当初計画では、東吾妻山(1974.7m)へも行く予定であったが、悪天候なので断念。直接、高山(1804.8m)へ向かうことにする。高山はピークまで樹林帯なので、吹雪で視界がなくても、何とか乗っ越せるであろうと判断した。

悪天候(雪)の磐梯吾妻スカイラインを、ラッセルを交代しながら道路の最高点(鳥子平)まで進む。

鳥子平から高山への登り。ラッセルが深いので交代しながら頑張って登る。ピーク直下はブッシュが鬱陶しい。

吹雪の高山ピークにて。ピークには電波の反射板が設置されており、ちょっと興ざめ。とにかく風が強いので、シールをつけたまま、風の当たらないところまで南側に降りてから、休憩。

休憩していたら、外国人をリーダとする5人パーティが後ろからやってきた。西吾妻からテント泊3泊4日で縦走してきたという。この日は、我々のトレースを辿って来たという。バージンスノーをいただくために、休憩もそこそこに、我々は滑降を開始した。雪が深いが、傾斜があるところでは、なかなかパウダースキーを堪能できる。快感!

思っていたほどブッシュも鬱陶しくなく、快適なツリーランを楽しむ。ただ、後半は斜度が緩いため、先頭の人はスキーが滑らないので歩く必要があるが、2番目以降の人は、トレース上に立っているだけで、滑っていける。皆で、先頭を譲りあいながら、下る。そうこうしていると、5人パーティが追いついてきて、抜きつ抜かれつしながら下山する。

1024.7mのポコは北側を捲いて、夏道に乗る。この先の夏道は、林道のように大きく切り開かれているので、写真のように、スキーは快調だ。

林道は先頭の人は滑らないが、2番目以降の人はトレース上なら滑るという微妙な傾斜。5人組パーティも含めて、先頭を譲り合いながら下る。長い林道だ。途中、男沼を眺めながら休憩(写真)。

銭谷号に2人乗り、高湯の石橋兄号の回収に行ってもらう。その間、留守番の2人(清原、山森)で、地元福島出身の札幌の斎藤(1987入部)に電話して、土湯での、おすすめの温泉等を紹介してもらう。その結果、お決まりの温泉は、斎藤のいとこの家である「ニュー扇屋」。湯上りには、自家製の「森山の温泉卵」をごちそうになる。とてもおいしい。皆、お土産に「森山の温泉卵」を買って帰った。
(文責:山森 聡)
- コメント (1)
OBの山行記録・ 2007年3月6日 (火)
湯ノ丸山(2101m)

●2007年1月28日(日)(1ー0)
【ルート】
地蔵峠→湯ノ丸山→旧鹿沢
【メンバ】
L:清原実(1986入部)、M:石橋岳志(1982入部)、山森聡(1986入部)

●2007年1月28日(日)(1ー0)
【ルート】
地蔵峠→湯ノ丸山→旧鹿沢
【メンバ】
L:清原実(1986入部)、M:石橋岳志(1982入部)、山森聡(1986入部)
【行程】
1月28日(日)(晴れ)地蔵峠:湯ノ丸スキー場リフト終点Co1840m(11:00)→湯ノ丸山2101m(12:00-15)→2098.5mポコ手前(南側)滑降点(12:20-30)→旧鹿沢スキー場ゲレンデ跡トップ(13:25)→鹿沢温泉(旧鹿沢)駐車場(14:00)
【地図】 (五万図)上田
【記録】

湯ノ丸スキー場のリフトは、たった100m登るだけで500円で、少々高い気がするが、リフトの機動力を活用しない手はない。湯ノ丸山へは、群馬県と長野県の県境の尾根を牧柵沿いにシール登高する。

湯ノ丸山ピークに到着した私(山森)。

山頂にいた人に、写真を撮ってもらう。左から、石橋兄、清原ババア、山森。

湯ノ丸山(2098.5m)から西側の烏帽子岳(2065.6m)を望む。

根子岳(ねこだけ)、四阿山(あずまやさん)方面を望む。四阿山は昨年1月中旬に行った際は、真っ白だったのに、今年はだいぶ黒い。やはり、昨年より相当に雪が少ないのだろう。

湯ノ丸山の北側のポコ手前から滑降開始。まずは山森が一番に飛び出した。

次に清原ババア。

そして石橋兄。

スキーが快調な斜面は、最初の数ターンで終わり。すぐに密林に突入した。ルートファインディングで失敗し、写真の樹林が一番上まで来ているあたりで、密林に突入してしまった。現役時代を含めた、いままでの山スキー経験で、一番不快調なブッシュスキーとなった。途中で、旧鹿沢スキー場のゲレンデ跡に出たが、雪が少ないのと、植林した潅木が成長したのとで、ブッシュが顔を出している斜面を滑ることになる。

旧鹿沢(下山口)から、地蔵峠(登山口)までは、ジャンケンで負けた人が、車道を歩いて車を回収に行く予定にしていたが、一緒に同じルートを下山したスノーボードのパーティの人の好意で、地蔵峠まで車に便乗させてもらって、車を回収してくる。お決まりの温泉は、旧鹿沢の紅葉館。温泉(\500-)とそば(\600-)のセットで、\1000-。

温泉(雲井乃湯)は、なかなか渋い。旧鹿沢温泉紅葉館は、「雪山讃歌」発祥の宿とのこと。昭和3年、西堀栄三郎(後の第一次南極越冬隊隊長)が京大山岳部の仲間と、吹雪で旧鹿沢温泉紅葉館に閉じ込められた際に、退屈しのぎに「雪山讃歌」を作詞したのだという。8年位前までは、鹿沢スキー場が営業していたとのことだが、スキー場が廃業してしまったので、訪れる人も少なく、まさに秘湯といった趣きだ。
(文責:山森 聡)
1月28日(日)(晴れ)地蔵峠:湯ノ丸スキー場リフト終点Co1840m(11:00)→湯ノ丸山2101m(12:00-15)→2098.5mポコ手前(南側)滑降点(12:20-30)→旧鹿沢スキー場ゲレンデ跡トップ(13:25)→鹿沢温泉(旧鹿沢)駐車場(14:00)
【地図】 (五万図)上田
【記録】

湯ノ丸スキー場のリフトは、たった100m登るだけで500円で、少々高い気がするが、リフトの機動力を活用しない手はない。湯ノ丸山へは、群馬県と長野県の県境の尾根を牧柵沿いにシール登高する。

湯ノ丸山ピークに到着した私(山森)。

山頂にいた人に、写真を撮ってもらう。左から、石橋兄、清原ババア、山森。

湯ノ丸山(2098.5m)から西側の烏帽子岳(2065.6m)を望む。

根子岳(ねこだけ)、四阿山(あずまやさん)方面を望む。四阿山は昨年1月中旬に行った際は、真っ白だったのに、今年はだいぶ黒い。やはり、昨年より相当に雪が少ないのだろう。

湯ノ丸山の北側のポコ手前から滑降開始。まずは山森が一番に飛び出した。

次に清原ババア。

そして石橋兄。

スキーが快調な斜面は、最初の数ターンで終わり。すぐに密林に突入した。ルートファインディングで失敗し、写真の樹林が一番上まで来ているあたりで、密林に突入してしまった。現役時代を含めた、いままでの山スキー経験で、一番不快調なブッシュスキーとなった。途中で、旧鹿沢スキー場のゲレンデ跡に出たが、雪が少ないのと、植林した潅木が成長したのとで、ブッシュが顔を出している斜面を滑ることになる。

旧鹿沢(下山口)から、地蔵峠(登山口)までは、ジャンケンで負けた人が、車道を歩いて車を回収に行く予定にしていたが、一緒に同じルートを下山したスノーボードのパーティの人の好意で、地蔵峠まで車に便乗させてもらって、車を回収してくる。お決まりの温泉は、旧鹿沢の紅葉館。温泉(\500-)とそば(\600-)のセットで、\1000-。

温泉(雲井乃湯)は、なかなか渋い。旧鹿沢温泉紅葉館は、「雪山讃歌」発祥の宿とのこと。昭和3年、西堀栄三郎(後の第一次南極越冬隊隊長)が京大山岳部の仲間と、吹雪で旧鹿沢温泉紅葉館に閉じ込められた際に、退屈しのぎに「雪山讃歌」を作詞したのだという。8年位前までは、鹿沢スキー場が営業していたとのことだが、スキー場が廃業してしまったので、訪れる人も少なく、まさに秘湯といった趣きだ。
(文責:山森 聡)
- コメント (0)
OBの山行記録・ 2007年3月5日 (月)
● 2007年3月

【ルート】
天の川、上ノ沢林道より大沼経由往復
【メンバ】
米山悟(84年入部)、野入善史(95年入部)、松田圭史(水産WVOB)
【行 程】
3月3日:湯ノ岱温泉→温泉から6キロ車(9:15)→Co535イグルー(14:30)
3月4日:C1(6:00)→大沼(7:30)→七ッ岳(9:00-15)→C1(10:30-11:00)→林道の車(13:30)
七ッ岳は大千軒岳の北にある、独立した山塊。標高こそ1000mを切るが、小さいながら七つの独立峰の名主だ。晴れた日に函館方面から遠くに見え、素人さんならあれは大千軒か?と間違えるほど格好良い山である。ブナの巨木の下にイグルーで泊まった。

【ルート】
天の川、上ノ沢林道より大沼経由往復
【メンバ】
米山悟(84年入部)、野入善史(95年入部)、松田圭史(水産WVOB)
【行 程】
3月3日:湯ノ岱温泉→温泉から6キロ車(9:15)→Co535イグルー(14:30)
3月4日:C1(6:00)→大沼(7:30)→七ッ岳(9:00-15)→C1(10:30-11:00)→林道の車(13:30)
七ッ岳は大千軒岳の北にある、独立した山塊。標高こそ1000mを切るが、小さいながら七つの独立峰の名主だ。晴れた日に函館方面から遠くに見え、素人さんならあれは大千軒か?と間違えるほど格好良い山である。ブナの巨木の下にイグルーで泊まった。
【記録】
 営林署の有料タケノコ園だったのに捜索騒ぎが多くて閉鎖された事で少し有名な、上ノ沢林道。湯ノ岱温泉からすぐに最終人家を過ぎ、どこまで車で行けるか走ったら、6キロ地点の沢の中で土木工事をしている現場があり、そこまでだった。ここから七ッ岳大沼まで、沢からゆるやかな尾根を延々15キロという気長な計画だ。
営林署の有料タケノコ園だったのに捜索騒ぎが多くて閉鎖された事で少し有名な、上ノ沢林道。湯ノ岱温泉からすぐに最終人家を過ぎ、どこまで車で行けるか走ったら、6キロ地点の沢の中で土木工事をしている現場があり、そこまでだった。ここから七ッ岳大沼まで、沢からゆるやかな尾根を延々15キロという気長な計画だ。
以前は林道歩きなんて楽しい山の前後にあるオツトメだと思っていたが、戦前の部報など読んでいると、林道の無い時代の、大きな川の渡渉や湿地や函を抜けていく苦労と楽しみを知り、それを追体験するのが面白く思うようになった。1日中林道歩きだが、林道が無ければもっと日数がかかる。夏に車で走ったらそれさえも思い至らない。
 10キロ進んだ頃に緩い尾根に乗る。気温は6度くらいで暖かい。もう何日も雪が降っていないので根雪の表面は締まっていて、ほとんど潜らない。僕はここまでスキーを引っ張った。尾根に上がると山全体がほとんどブナだった。ブナの山は樹間が整っていて、清々しい。スキーするのにも丁度良い森になる。久しぶりの山で調子が出ないメンバーもいたので、Co530あたりでイグルーを作った。ブナ林の中から目指す七ッ岳を見る天場だ。三角に聳え、形のよい山だ。
10キロ進んだ頃に緩い尾根に乗る。気温は6度くらいで暖かい。もう何日も雪が降っていないので根雪の表面は締まっていて、ほとんど潜らない。僕はここまでスキーを引っ張った。尾根に上がると山全体がほとんどブナだった。ブナの山は樹間が整っていて、清々しい。スキーするのにも丁度良い森になる。久しぶりの山で調子が出ないメンバーもいたので、Co530あたりでイグルーを作った。ブナ林の中から目指す七ッ岳を見る天場だ。三角に聳え、形のよい山だ。
 林道をショートカットした小高い丘の上に、この山で見かけたブナの中で最も大きく立派な一本がある。その下にイグルーを作った。直径は1.5m以上、高さは18mあまり。広げた枝の幅が、これまた10m近い。イグルーどころか神社を祀りたい位だ。夜は枯れ木で焚き火する。焚き火はお湯がふんだんに出来るので、脱水症状にもよいし、安心して濃い酒を飲める。野入君が上等の酒を持ってきてくれた。この春就職が決まった松田君を祝った。雪の状態、気温などあわせて、4月の様だ。今年は厳冬期が無く、季節が一月進んでしまっている。
林道をショートカットした小高い丘の上に、この山で見かけたブナの中で最も大きく立派な一本がある。その下にイグルーを作った。直径は1.5m以上、高さは18mあまり。広げた枝の幅が、これまた10m近い。イグルーどころか神社を祀りたい位だ。夜は枯れ木で焚き火する。焚き火はお湯がふんだんに出来るので、脱水症状にもよいし、安心して濃い酒を飲める。野入君が上等の酒を持ってきてくれた。この春就職が決まった松田君を祝った。雪の状態、気温などあわせて、4月の様だ。今年は厳冬期が無く、季節が一月進んでしまっている。
 朝起きると霧の中だった。視界100m以下の中、小沼を経て大沼まで。このあたりでは林道はあまり林道らしくなく、緩やかなブナの林を行くようだ。霧の大沼の対岸に、七ッ岳直下の標高差100mの壁の足元が見える。最低コル目指して磁石で進み、基部からは時折の晴れ間でコルを確認して、急斜面を登る。前半スキー、後半シートラで稜線にあがり、そこでシーデポして山頂をツボ足で往復する。山頂では、霧の雲海に沈む七ッ岳大沼とブナ林、それに意外に遠くに大千軒岳連峰が真っ白く聳えていた。高曇りと雲海に挟まれ海も見えなかったが、この山が周囲の中で抜き出た孤峰であり、狭くて急斜面に囲まれた山頂が気持ちよかった。
朝起きると霧の中だった。視界100m以下の中、小沼を経て大沼まで。このあたりでは林道はあまり林道らしくなく、緩やかなブナの林を行くようだ。霧の大沼の対岸に、七ッ岳直下の標高差100mの壁の足元が見える。最低コル目指して磁石で進み、基部からは時折の晴れ間でコルを確認して、急斜面を登る。前半スキー、後半シートラで稜線にあがり、そこでシーデポして山頂をツボ足で往復する。山頂では、霧の雲海に沈む七ッ岳大沼とブナ林、それに意外に遠くに大千軒岳連峰が真っ白く聳えていた。高曇りと雲海に挟まれ海も見えなかったが、この山が周囲の中で抜き出た孤峰であり、狭くて急斜面に囲まれた山頂が気持ちよかった。
直下の急斜面は落雪ブロックがごろごろしていてあまり突撃滑降出来なかったが、基部から下、C1超えてずいぶん下まではスキーにほどよい傾斜で、楽しく滑って来た。だいたいブナの生えているところはスキーが快調だ。林道をスイコスイコと漕いで下山。町営湯ノ岱温泉は値打ちものだった。広い浴場に高温中温低温の源泉があり、床は湯ノ花で無数の扇模様。しかも350円の低価格だ、泣ける。くつろぎ部屋の雰囲気も相当砕けている。お品書きも豊富だった。偶然にも、結氷の間宮海峡徒歩横断男とも出会ったりして。木古内のあおき食堂でカツ丼を掻ッ込み、海峡を見ながら函館へ。
 営林署の有料タケノコ園だったのに捜索騒ぎが多くて閉鎖された事で少し有名な、上ノ沢林道。湯ノ岱温泉からすぐに最終人家を過ぎ、どこまで車で行けるか走ったら、6キロ地点の沢の中で土木工事をしている現場があり、そこまでだった。ここから七ッ岳大沼まで、沢からゆるやかな尾根を延々15キロという気長な計画だ。
営林署の有料タケノコ園だったのに捜索騒ぎが多くて閉鎖された事で少し有名な、上ノ沢林道。湯ノ岱温泉からすぐに最終人家を過ぎ、どこまで車で行けるか走ったら、6キロ地点の沢の中で土木工事をしている現場があり、そこまでだった。ここから七ッ岳大沼まで、沢からゆるやかな尾根を延々15キロという気長な計画だ。以前は林道歩きなんて楽しい山の前後にあるオツトメだと思っていたが、戦前の部報など読んでいると、林道の無い時代の、大きな川の渡渉や湿地や函を抜けていく苦労と楽しみを知り、それを追体験するのが面白く思うようになった。1日中林道歩きだが、林道が無ければもっと日数がかかる。夏に車で走ったらそれさえも思い至らない。
 10キロ進んだ頃に緩い尾根に乗る。気温は6度くらいで暖かい。もう何日も雪が降っていないので根雪の表面は締まっていて、ほとんど潜らない。僕はここまでスキーを引っ張った。尾根に上がると山全体がほとんどブナだった。ブナの山は樹間が整っていて、清々しい。スキーするのにも丁度良い森になる。久しぶりの山で調子が出ないメンバーもいたので、Co530あたりでイグルーを作った。ブナ林の中から目指す七ッ岳を見る天場だ。三角に聳え、形のよい山だ。
10キロ進んだ頃に緩い尾根に乗る。気温は6度くらいで暖かい。もう何日も雪が降っていないので根雪の表面は締まっていて、ほとんど潜らない。僕はここまでスキーを引っ張った。尾根に上がると山全体がほとんどブナだった。ブナの山は樹間が整っていて、清々しい。スキーするのにも丁度良い森になる。久しぶりの山で調子が出ないメンバーもいたので、Co530あたりでイグルーを作った。ブナ林の中から目指す七ッ岳を見る天場だ。三角に聳え、形のよい山だ。 林道をショートカットした小高い丘の上に、この山で見かけたブナの中で最も大きく立派な一本がある。その下にイグルーを作った。直径は1.5m以上、高さは18mあまり。広げた枝の幅が、これまた10m近い。イグルーどころか神社を祀りたい位だ。夜は枯れ木で焚き火する。焚き火はお湯がふんだんに出来るので、脱水症状にもよいし、安心して濃い酒を飲める。野入君が上等の酒を持ってきてくれた。この春就職が決まった松田君を祝った。雪の状態、気温などあわせて、4月の様だ。今年は厳冬期が無く、季節が一月進んでしまっている。
林道をショートカットした小高い丘の上に、この山で見かけたブナの中で最も大きく立派な一本がある。その下にイグルーを作った。直径は1.5m以上、高さは18mあまり。広げた枝の幅が、これまた10m近い。イグルーどころか神社を祀りたい位だ。夜は枯れ木で焚き火する。焚き火はお湯がふんだんに出来るので、脱水症状にもよいし、安心して濃い酒を飲める。野入君が上等の酒を持ってきてくれた。この春就職が決まった松田君を祝った。雪の状態、気温などあわせて、4月の様だ。今年は厳冬期が無く、季節が一月進んでしまっている。 朝起きると霧の中だった。視界100m以下の中、小沼を経て大沼まで。このあたりでは林道はあまり林道らしくなく、緩やかなブナの林を行くようだ。霧の大沼の対岸に、七ッ岳直下の標高差100mの壁の足元が見える。最低コル目指して磁石で進み、基部からは時折の晴れ間でコルを確認して、急斜面を登る。前半スキー、後半シートラで稜線にあがり、そこでシーデポして山頂をツボ足で往復する。山頂では、霧の雲海に沈む七ッ岳大沼とブナ林、それに意外に遠くに大千軒岳連峰が真っ白く聳えていた。高曇りと雲海に挟まれ海も見えなかったが、この山が周囲の中で抜き出た孤峰であり、狭くて急斜面に囲まれた山頂が気持ちよかった。
朝起きると霧の中だった。視界100m以下の中、小沼を経て大沼まで。このあたりでは林道はあまり林道らしくなく、緩やかなブナの林を行くようだ。霧の大沼の対岸に、七ッ岳直下の標高差100mの壁の足元が見える。最低コル目指して磁石で進み、基部からは時折の晴れ間でコルを確認して、急斜面を登る。前半スキー、後半シートラで稜線にあがり、そこでシーデポして山頂をツボ足で往復する。山頂では、霧の雲海に沈む七ッ岳大沼とブナ林、それに意外に遠くに大千軒岳連峰が真っ白く聳えていた。高曇りと雲海に挟まれ海も見えなかったが、この山が周囲の中で抜き出た孤峰であり、狭くて急斜面に囲まれた山頂が気持ちよかった。直下の急斜面は落雪ブロックがごろごろしていてあまり突撃滑降出来なかったが、基部から下、C1超えてずいぶん下まではスキーにほどよい傾斜で、楽しく滑って来た。だいたいブナの生えているところはスキーが快調だ。林道をスイコスイコと漕いで下山。町営湯ノ岱温泉は値打ちものだった。広い浴場に高温中温低温の源泉があり、床は湯ノ花で無数の扇模様。しかも350円の低価格だ、泣ける。くつろぎ部屋の雰囲気も相当砕けている。お品書きも豊富だった。偶然にも、結氷の間宮海峡徒歩横断男とも出会ったりして。木古内のあおき食堂でカツ丼を掻ッ込み、海峡を見ながら函館へ。
- コメント (2)
現役の報告・ 2007年3月2日 (金)
【年月日】2007年2月16〜18日(3ー0)
【ルート】 凌雲岳北尾根
【メンバ】L勝亦(4 )AL平塚(3)
1日目 雪後曇 陸万別バス停(7:30)-・1461付近=Ω1(15:20)
陸万別川沿いの林道は除雪なし。国道からラッセル。ラッセルすねから膝。Co550二股を左股へ行き、Co580の氷爆直前で左岸に渡り林道(ブル道?)を使って捲く。沢中を行くのはきついので尾根に上がる。尾根上しばらくブル道があった。ブル道は・912の尾根を登っているようだったので、途中で東にそれる。尾根に上がる急斜面は一部つぼ。・ラッセルのせいで時間がかかったので、・1461付近で穴Ω1。
2日目 晴 Ω1(6:00)-P3(12:10)-P3ab終了(12:40)-Ω1=Ω2(15:10)
主に東側にセッピ張り出している。P1のまきは、西側ブッシュの中。P2(上川岳手前の岩稜)は西側のブッシュの中を捲く。P3は岩の基部から取り付き、やや東側を登る。1p目(L)凹角を2つ抜ける。ハイマツまで。2p目(L)雪田と一部岩登り。残置ハーケンまで。時間切れになったので2pabして帰る。帰りは来た道。Ω1=Ω2。
3日目 曇時々雪 Ω2(6:30)-バス停(9:30)
来た道滑って下山。帰りは最後除雪が入っていてシートラやシーズリ。
よかった。
ちょっと、おすすめです。
【ルート】 凌雲岳北尾根
【メンバ】L勝亦(4 )AL平塚(3)
1日目 雪後曇 陸万別バス停(7:30)-・1461付近=Ω1(15:20)
陸万別川沿いの林道は除雪なし。国道からラッセル。ラッセルすねから膝。Co550二股を左股へ行き、Co580の氷爆直前で左岸に渡り林道(ブル道?)を使って捲く。沢中を行くのはきついので尾根に上がる。尾根上しばらくブル道があった。ブル道は・912の尾根を登っているようだったので、途中で東にそれる。尾根に上がる急斜面は一部つぼ。・ラッセルのせいで時間がかかったので、・1461付近で穴Ω1。
2日目 晴 Ω1(6:00)-P3(12:10)-P3ab終了(12:40)-Ω1=Ω2(15:10)
主に東側にセッピ張り出している。P1のまきは、西側ブッシュの中。P2(上川岳手前の岩稜)は西側のブッシュの中を捲く。P3は岩の基部から取り付き、やや東側を登る。1p目(L)凹角を2つ抜ける。ハイマツまで。2p目(L)雪田と一部岩登り。残置ハーケンまで。時間切れになったので2pabして帰る。帰りは来た道。Ω1=Ω2。
3日目 曇時々雪 Ω2(6:30)-バス停(9:30)
来た道滑って下山。帰りは最後除雪が入っていてシートラやシーズリ。
ちょっと、おすすめです。
- コメント (0)
 HOME
HOME
 メニュー
メニュー